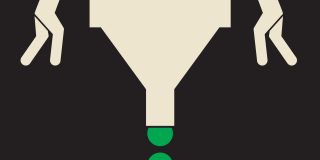「民法改正を行った民法177条(不動産物権変動)に対応したい」
上記のように考えている方も多いでしょう。
本記事では物権変動について規定している 民法177条 にフォーカスします。
不動産登記や公示の原則、民法177条における第三者について詳しく見ていきます。(改正民法対応)
- 民法177条の不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない
- 民法177条の第三者は当事者とその包括承継人(その具体例としては相続人)以外の者
- 民法177条のルールを過去問の例題で押さえられる
- 宅建試験に最短合格できる方法がまとめで分かる
- 宅建士の資格を最短で取得するなら、勉強のモチベーション維持に特化したスタケンの利用がおすすめ

\ 合格時全額返金キャンペーン/
この記事で学べること
民法177条 (不動産物権変動)の規定

時効や相続による不動産取得の公示も登記が必要なの?
民法177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と規定しています。
「不動産に関する物権の得喪及び変更」とは、言い換えれば「すべての物権変動」です。
つまり日本の民法は、文面だけを見るのであれば、「不動産を取得したり譲渡したり、もちろん時効や相続のときも、とにかく不動産に何かあったら登記しておかないと第三者に対抗できないよ」と規定しているのです。
しかし、かつての日本の民法解釈においては、実は「相続や時効は登記がなくても対抗できる」というのが通説・判例でした。
理由は、日本の民法が120年前にヨーロッパから輸入された、という歴史にあります。
ドイツやフランスの民法では、登記をもって公示することが必要とされている不動産物権変動は、意思表示によって生じた不動産物権変動(たとえば、売買契約による所有権移転)に限られています。相続や時効により所有権を取得したような場合(意思表示によらない場合)は、公示するのに登記は要らないのです。
それならば、ヨーロッパから輸入した日本の民法も同じように解釈すべきだろう。そんな意見が出るのも当然でしょう。故に、大昔においては、日本でも「相続や時効は登記がなくても対抗できる」というのが通説・判例だったのです。
しかし、どうしても解決できない問題がありました。
ドイツやフランスの民法は、「意思表示による不動産物権変動」であることを明記しているのですが、そもそも日本の民法は、そのようなことが明記されていません。
また、不動産物権変動に登記を要求する理由は、不動産取引の安全を保護しようという目的のためです。
そうすると、意思表示を要素とする契約などによる取得の場合と、意思表示を要素としない相続や時効による取得の場合とをわざわざ区別することで、後者の取引の安全保護が果たされないことにもなりかねません。
そこで、現在の通説・判例は、わざわざヨーロッパ式に読み変えることをやめました。
文言どおり、意思表示に限らず、すべての不動産物権変動について登記が必要であるとの見解を採用しているのです(無制限説)。
登記が必要な物権変動にはどのようなものがあるの?
① 法律行為の取消(121条)・解除(545条)
法律行為の取消・解除をした場合は、取消後・解除後に取引関係に入った第三者に対しては登記がなければ対抗できません。
② 死因贈与(554条)
死因贈与が取り消すことができない場合でも、その目的たる不動産を贈与者が第三者に売り渡したときは有効であり、受贈者と買主との関係は対抗関係となります。
③ 特定遺贈(985条)
不動産の遺贈を受けた者は、その旨の所有権移転登記を経由しないと第三者に対抗することができません。
④ 遺産分割(909条)
相続財産中の不動産につき、遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対抗することができません。
⑤ 時効取得(162条)
時効完成後の第三者に対しては、登記がない限り時効による所有権取得を対抗することができません。
⑥ 法定地上権(388条)
当事者間では問題となりませんが、競落人から土地を譲り受けた第三者に対しては、建物所有者は、建物所有権の登記がなければ法定地上権を対抗できません。
⑦ 競売
強制・任意競売に基づく競落による物権の取得を対抗するには、登記が必要となります。
民法177条の「第三者」って誰をいうの?

「第三者」は当事者以外?
民法177条によると、不動産物権変動は、登記がないとこれを「第三者」に対抗することができません。
これを反対解釈すると、不動産物権変動があっても、ある人が民法177条にいう「第三者」に該当しないのであれば、登記は必要ないということになります。そこで、この「第三者」とはどのような人を意味するのかが重要な問題となります。
一般に、「第三者」とは、当事者とその包括承継人(その具体例としては相続人)以外の者を意味します。では、この当事者とは誰のことをいうのでしょうか。
たとえば、AがBにその所有する土地を売却したとすると、Aが当事者であることに問題はありません。しかし、Bが登記のないまま20年間その土地を占有しており、その間にAがCに当該土地を二重に売却し、Cが登記を具備した場合、Cは当事者といえるでしょうか。
この場合、BがCに対してその土地を時効取得したと主張できますが、CはBからみて当事者であり、Bは登記がなくてもCに対応できるとするのが一般です。
つまり、物権変動の場面において当事者とは、物権変動により直接法律上の効果を受ける者を意味するのであって(CはBが取得時効を主張することにより権利を喪失するという直接の法律上の効果を受ける)、物権行為の当事者だけを意味するものではないとされているのです。
・AからCへの土地売却(二重譲渡2):当事者はAとC、第三者はB
・Bが時効によりCの土地を取得:当事者はBとC、第三者はいない
⇒Bの時効取得については、BもCも当事者であるため、Bは「登記なし」でも土地取得を主張可
ところで、不動産登記法は、当事者及びその包括承継人以外の者でも、「詐欺又は強迫により登記の申請を妨げた第三者」と「他人のために登記を申請する義務のある者」は登記がないことを主張することができないと規定しています(5条)。
たとえば、Aが所有する土地をBが購入し登記しようとしていたところ、CがBを騙したり強迫したりして登記を妨害している間に、Aからその土地を購入し登記をしたとしても、BはCに対して登記なくして土地の所有権を主張できます。
また、Bが登記をすることをCに委託したにもかかわらず、CがBのために登記をせずに、Aからその土地を購入してC名義の登記をした場合なども、同じく、BはCに対して登記なくして土地の所有権を主張できるということです。
つまり、不動産登記法に規定されているこれらの者は、民法177条にいう「第三者」には含まれないといえそうです。
では、それ以外の者はすべて「第三者」といえるのでしょうか。
たとえば、Aがその所有する土地をBに売却したが、登記は依然としてAのままであった。そこで、日頃からBに恨みを抱いていたCは、Bを困らそうとして、Aからその土地を二重に譲り受け、自己名義の登記をした。
Bを困らすという意図をもった者も、民法177条にいう「第三者」であるとして、Bは登記がない以上Cにその所有権取得を主張できないのでしょうか。
この点、できないとする見解もあります(無制限説)。
しかし、通説・判例は、不動産に関して取引上正当な利害関係をもっていない者を第三者として保護する必要はないという認識のもとで、民法177条にいう「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、不動産物権変動の登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者としています。
この通説・判例からは、上記の例のCは正当な利益を有する者とはとても言えないので、Bは、登記なくして土地の所有権をCに主張することができるという結論に至ります。ちなみに、Cのような地位にある者を「背信的悪意者」と呼びます。
背信的悪意者とは誰のこと?
背信的悪意者とは、判例上、「実体上物権変動があった事実を知りながら当該不動産について利害関係を持つに至ったものにおいて、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある」者をいうと定義されています(最判昭和44年1月16日)。
「第三者」にあたる具体例
① 譲受人
- 二重譲渡における譲受人相互間
- 被相続人が不動産を贈与したが、その旨の登記がなされていなかった場合に、その相続人からその不動産を買い受けた者
- 地上権設定登記がされたと地上の建物を地上権とともに譲り受けた者は、地上権登記がなければ土地の譲受人に地上権を対抗できない。ただし、建物所有を目的とする地上権者は、と地上に登記ある建物を所有すれば地上権を第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。
② 差押債権者
不動産につき寄贈による移転登記がなされない間に、共同相続人の1人に対する強制執行として、その持分を差押えた者。
③ 賃借人
他人に賃貸中の土地を譲り受けた者は、所有権移転登記を経由しなければ賃借人に所有権を対抗しえず、賃貸人たる地位を取得したことも主張できない。すなわち、賃料請求・賃借人の債務不履行に基づく解除権行使・賃貸借終了に基づく明渡請求をすることができない。
④ 共有者
不動産の共有者の1人が自己の持分を譲渡した場合の、他の共有者。
⑤ 背信的悪意者からの転得者
不動産の二重譲渡において、第二買主たる背信的悪意者から当該不動産を譲り受け、登記も具備した者(転得者)は、自分自身が第一買主に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、その不動産の取得を第一買主に対抗することができる。
⑥制限物権取得者
⑦強制執行における買受人
「第三者」にあたらない具体例
① 無権利者
- 登記簿上所有者として表示されているにすぎない架空の権利者
- 遺言執行者いる場合において相続人から遺贈不動産を譲り受けた者
- 目的物の仮装譲受人
- 消滅した債権を被担保債権とする抵当権者
- 相続を放棄した者からの相続財産譲受人
② 不法行為者・不法占拠者
二重譲渡された未登記建物を第三者が不法行為により毀損した場合は、各譲受人は建物登記を備えずに第三者に損害賠償請求できます。
③ 背信的悪意者
- 第三者が自己の行為と矛盾した態度をとり、信義則(禁反言)に照らしてこれを認め難い場合
- 第一買主に高値で売りうけようとして買い受けた場合
- 第一買主に害意をもって積極的に売主を教唆して売らせた場合
- 詐欺・強迫により登記申請行為を妨げた場合
④ 所有権が輾転移転した場合の前主
まとめ ~過去問を解いてみよう!~

A所有の甲土地についての所有権移転登記と権利の主張に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(2012年度問6)
1 甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。
2 甲土地の賃借人であるDが、甲土地上に登記ある建物を有する場合に、Aから甲土地を購入したEは、所有権移転登記を備えていないときであっても、Dに対して、自らが賃貸人であることを主張することができる。
3 Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。
4 Aが甲土地をHとⅠとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にⅠが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Ⅰがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。
正解:4
【解説】
1 ×
不動産について時効が完成しても、その登記がなければ、その後にその不動産を購入して登記を得た第三者に対しては時効による権利の取得を対抗できないのに対して、第三者がその不動産を購入して登記した後に時効が完成した場合においては、その第三者に対しては、登記を得ていなくても時効取得をもってこれに対抗することができます(最判昭和41年11月22日)。したがって、Bは甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して時効による所有権の取得を主張できます。
2 ×
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しない限り、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができません(最判昭和49年3月19日)。宅地の賃借人と宅地の所有権を取得した者との関係は対抗関係となるからです(民法177条)。したがって、所有権移転登記をまだ行っていないEは、建物の所有権を主張できず、またこの建物の賃貸人の地位も主張することができません。
3 ×
不動産の取得等は、原則として、登記を備えなければ、正当の利益を有する第三者に主張できません(民法177条)。不動産が二重に売買された場合も、特段の意思表示がないかぎり、一方の買主は所有権の登記を備えなければ、他方の買主に所有権を主張できません。結果的には先に登記を備えた方が所有権を取得します。契約の先後ではなく登記の先後で所有権の帰属が決まります。したがって、Gは、登記がなければ、Fに対して自らが所有者であることを主張できません。
4 ○
背信的悪意者は正当の利益を有する第三者にあたりません(最判昭和43年8月2日)。本問のように、Iが背信的悪意者に当たるとしても、Jは、Hに対する関係でJ自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、甲土地の所有権取得をもってHに対抗することができます(最判平成8年10月29日)。したがって、Hは所有権移転登記を備えていない以上、Jに対して自らが所有者であることを主張することができません。
さて、「民法177条」に規定される第三者にフォーカスして解説しましたが、いかがでしたか。
物権変動は宅建試験の頻出分野です。しっかり押さえて、確実に1点を取りにいきましょう。
なお、本記事で物件変動について理解しきれなかった方は、試験攻略に特化した動画講義+ライバルとなる宅建受験生と交流できる進捗相談会を用意しているスタケンのサービスをおすすめします。
スタケンのサービスについて、「スタケン®のサービス内容|合格圏内を突破する勉強法も徹底解説」の記事を参考にしましょう。
\ 合格時全額返金キャンペーン/
最新記事 by 田中 謙次 (全て見る)
- 【宅建民法を攻略】公示の原則~民法177条における第三者とは~ - 2019年6月21日
- 【宅建民法を攻略】公信の原則~見た目を信じちゃいけない?~ - 2019年6月14日
- 【宅建民法を攻略】物権~所有権は争いのもと?~ - 2019年6月5日
- 【宅建民法を攻略】時効~時が経てば解決する?~ - 2019年5月21日