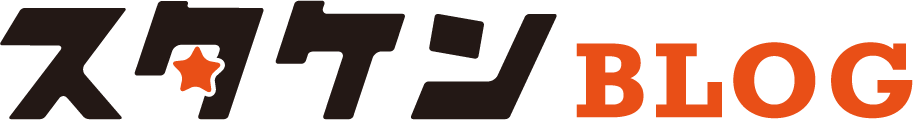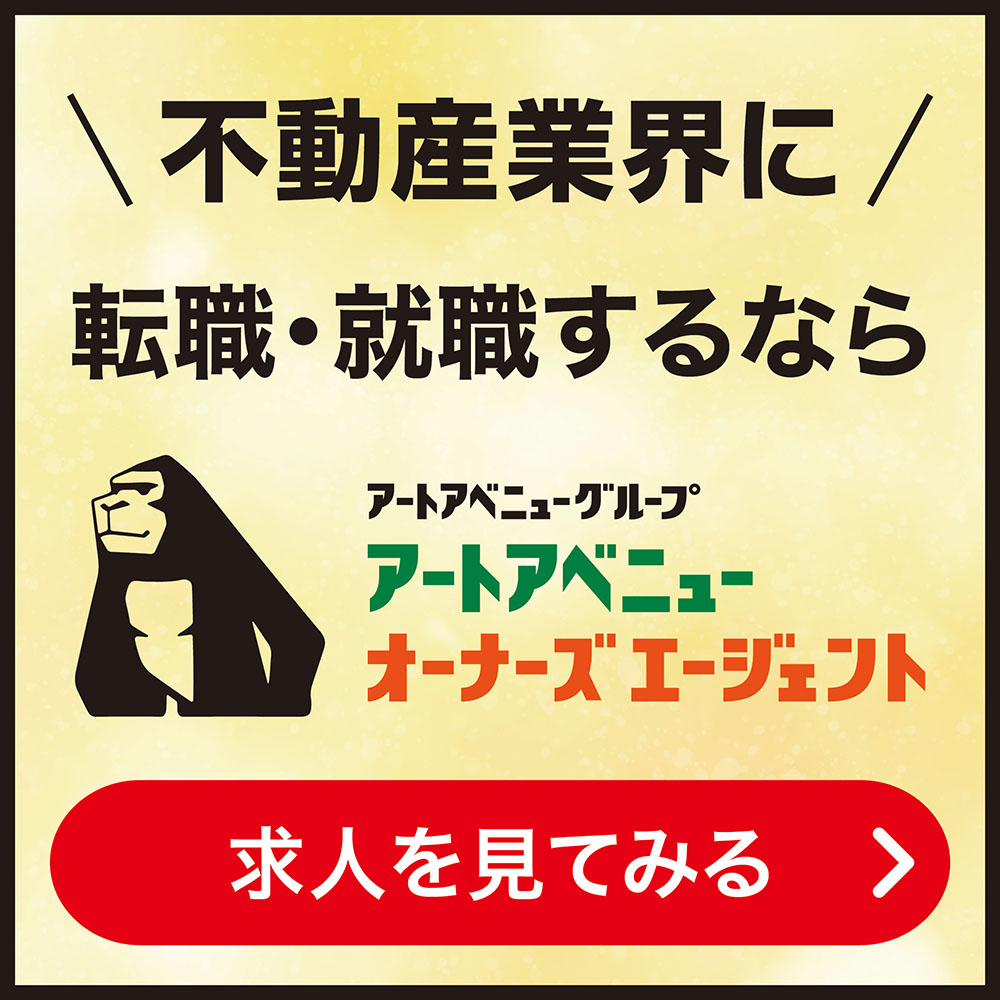不動産業界や不動産に関わる資格の中でも、知名度・人気度がトップクラスの宅建。
宅建の受験者数は少しずつ増加しており、合格者も増えている一方で、受からない人も一定数存在しています。
実際に毎年の合格率は15%前後なので、8割以上の人が不合格となってしまう難関資格です。
宅建を受ける方の中には、受からないことを考えて不安を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
宅建試験に合格するために必要なのは、受からない人の特徴を押さえ、その通りに行動することです。
この記事では、宅建に受からない人がどのぐらいいるのか、宅建に受からない人の特徴について解説します。
- 宅建に受かる人・受からない人が何人くらいいるか、過去10年のデータで分かる
- 宅建に受からない人の特徴が分かる
- 宅建に受からない人と反対の行動を取れば合格に近づく
- 不動産業界の就職・転職なら積極採用中のアートアベニューグループがおすすめ
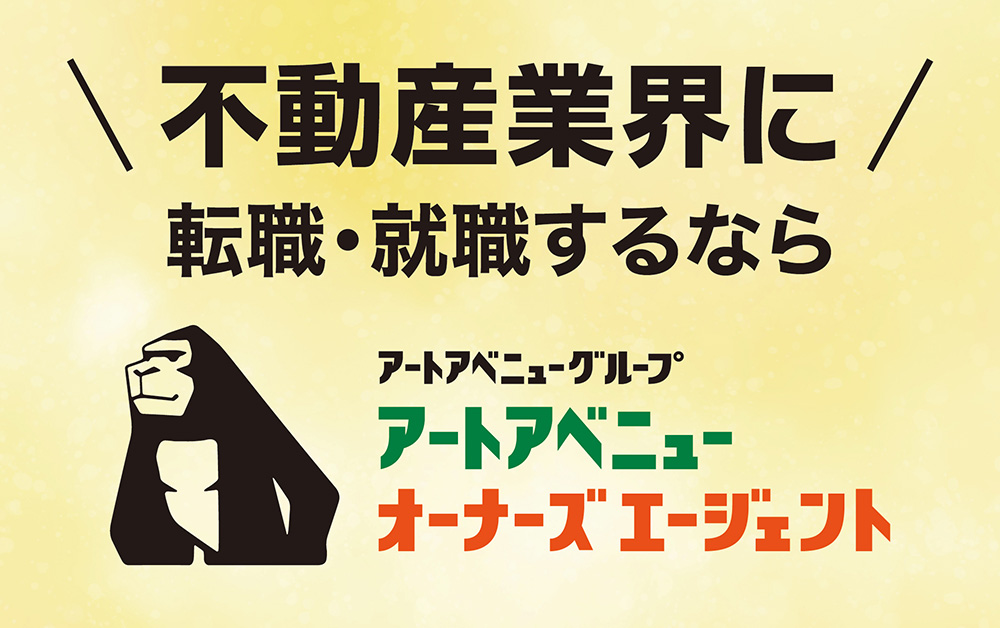
\ 積極採用中!/
この記事で学べること
宅建に受からない人はどれくらいいる?合格率調査
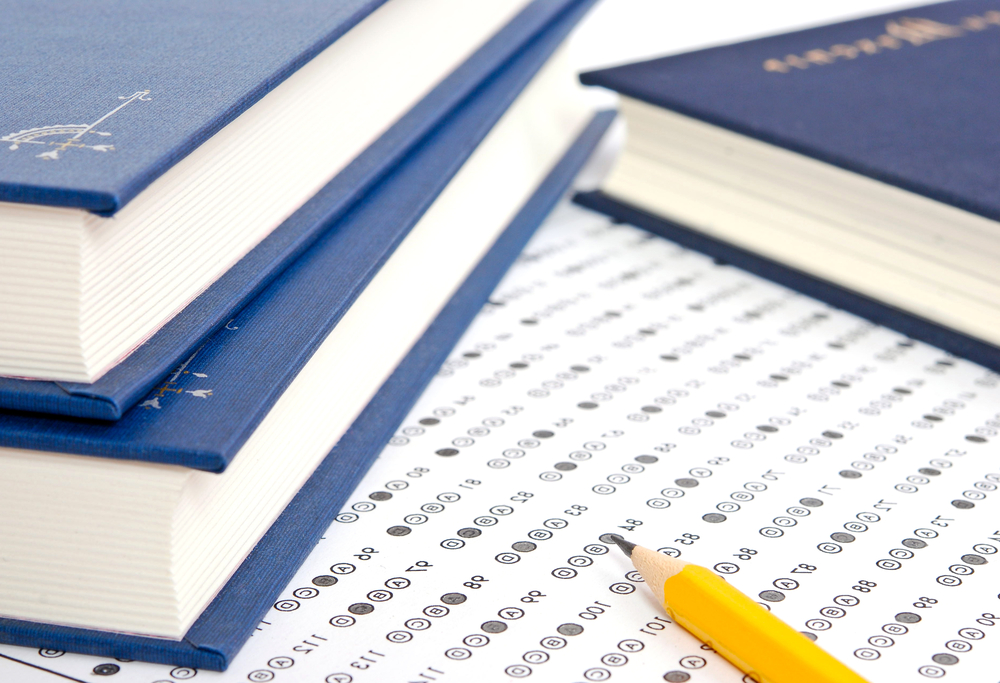
まずは、宅建に受からない人がどれくらいいるかを知るために、近年の合格率を確認しましょう。
宅建の合格率は13〜17%を推移しています。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格ライン(点) |
| 令和6年度 | 241,436人 | 44,992人 | 18.6% | 37点 |
| 令和5年度 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% | 36点 |
| 令和4年度 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% | 36点 |
| 令和3年度(12月) | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% | 34点 |
| 令和3年度(10月) | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% | 34点 |
| 令和2年度(12月) | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% | 36点 |
| 令和2年度(10月) | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% | 38点 |
| 令和元年度 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% | 35点 |
| 平成30年度 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% | 37点 |
| 平成29年度 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% | 35点 |
| 平成28年度 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% | 35点 |
| 平成27年度 | 194,926人 | 30,028人 | 15.4% | 31点 |
| 平成26年度 | 192,029人 | 33,670人 | 17.5% | 32点 |
20万人受けてその年の合格率が15%だった場合、受かる人は3万人、受からない人は17万人です。
宅建は、落ちる人のほうが圧倒的に多い資格試験です。
宅建に何回で合格する人が多い?
宅建は「一発で受かった!」という人も一定数存在していますが、「何回受けても落ちる」という人もいます。
しかし、一般的には合格する人の平均受験回数は約2回といわれています。
「それだったら1回落ちても問題ないかな」と考える方も多そうですが、宅建に合格した人の内、40%以上の方が1回で合格しています。
ちなみに2回目で合格した方が約30%で合格しているので、70%の人は2回以内に合格していることがわかります。
受験回数を重ねる度に合格率が下がっていくため、一発合格を目標にしましょう。
プロ以外のアドバイスを信じすぎない!まぐれや勉強効率が良い人もいる
宅建を持っているけど予備知識の幅が広い法律の専門家など、宅建受験のプロではない人の学習ノウハウはよく公開されています。
「勉強に慣れていない」「試験のコツがわかっていない」という人は、宅建受験のプロではない人の勉強方法を聞くのはいいと思います。
しかし、これらの専門家のアドバイスを信じすぎるのはおすすめできません。
なぜなら、法律の専門家は高学歴の方が多く試験勉強にも慣れているため、圧倒的に効率の良い方法で宅建勉強を進められるからです。
例えば、宅建試験は300時間の勉強時間が必要といわれていますが、予備知識があったり効率の良い勉強ができたりすると、100時間以下の勉強時間でも宅建に合格することは可能です。
しかし、これらのアドバイスは勉強に対する慣れが必須なので、勉強に慣れていない方や他の資格を保有していない方にとっては非現実的な内容という場合も少なくありません。
アドバイスを参考にする場合は、自分の勉強そのものに対する理解度に合わせてアドバイスをしてくれるプロの宅建講師のアドバイスを参考にしましょう。
なお、プロの宅建講師のアドバイスを受けたい方は、宅建通信講座の受講をおすすめします。
宅建試験は難化している?
宅建試験は難化傾向にあると言われています。
宅建試験が国家資格になりどうしても取りたいという人が増えたので、受験生のレベルが上がったにも関わらず、合格率は変わっていません。
つまり、以前は受かる学力があった人が落とされるようになっているということです。
宅建試験を受験する場合は、徹底した対策が必要と言えるでしょう。
宅建に受からない人の特徴

宅建に受からない人には、次のような特徴があります。
- 宅建試験の内容がわかっていない
- やみくもに過去問を解いている
- 勉強に時間を取らない
- 勉強にお金をかけない
1.宅建試験の内容がわかっていない
そもそも宅建とはどのような試験なのかを知れなければ、どのように勉強を進めれば良いのかわかりませんね。
ここからは、宅建試験の内容を簡単に説明します。
【4科目の内訳】権利関係
権利関係の問題は14問出題されます。権利関係は民法という法律の知識が問われます。
民法の言い回しや用語は独特で、法律を勉強したことがない人には内容を理解するのが難しいです。
例えば、民法では「知っている=善意」「知らない=悪意」と言います。
法律を覚える際は、法律を唱える弁護士の気分で口に出しながら勉強すると頭に入りやすいので、実践してみましょう。
【4科目の内訳】宅建業法
宅建業法に関する問題は20問出題されます。
この部分は得点源になりやすいため、20問満点を目指して勉強しましょう。
暗記することが重要で、ひっかけ問題が多いです。
暗記メインなので、間違い探しで遊ぶように楽しみながら問題を解くことをおすすめします。
【4科目の内訳】法令上の制限
法令上の制限に関する問題は、8問出題されます。
こちらも暗記ですが、理論や考えを一緒に覚えることをおすすめします。
例えば、非常用昇降機は31m超の建物につけなければなりませんが、なぜ31mなのかを考えると覚えやすいです。
【4科目の内訳】税その他
税その他に関する問題は、8問出題されます。
3問は税に関する問題で、5問は統計などです。
税金はとても幅広く、どれも似たような税制なので暗記が難しいです。
そのため、得点源の宅建業法が完璧でなければ、宅建業法に時間を費やしましょう。
あとは、それぞれの科目について勉強しながら感覚を掴みましょう。
勉強しているうちにさらに問題の出題の傾向や、独特の言い回しが掴めてきます。
2.やみくもに過去問を解いている
宅建試験はやみくもに問題を解いているだけでは身になりません。
宅建の勉強は過去問を解けば合格できるとほとんどの方が言います。
確かにその通りなのですが、実際は「テキストや参考書で覚えた内容を活かし、初見で過去問を解いて合格ラインを超える」という条件付きの話です。
また、過去問を何度も解いていると問題を覚えてしまいます。
問題を覚えても本試験では同じ内容が出題されないので、あまり意味はありません。
- 問題の解き方
- 誤っている選択肢のどこが間違っているか
上記のポイントを理解しないと、初見問題に対応することは難しいです。
過去問1年分であれば50問で4つの選択肢があるので、間違いの選択肢もなぜ間違っているかを解答できるようになり、200問全て正解できるように勉強しましょう。
3.勉強に時間を取らない
勉強の質が高くても、時間を取らなければ合格を勝ち取ることは難しいでしょう。
- 仕事を早く切り上げる
- 飲み会を断る
- 友達や恋人に理解してもらい数ヶ月間遊ぶのを辞める
- 家事は諦めて業者に頼む
- 家族に頼る
上記のように、削れる時間はたくさんあります。
例えば断酒はおすすめです。
たとえ参加しなければならない会社の飲み会があっても「断酒してるので〜」と普段から周りに言っておけば、今の時代飲まなくても強要されませんし、帰ってから勉強の時間が取れます。
社会人の方は有給も、楽しい夏休みも宅建勉強に時間を割くことになりますが、数か月の辛抱なので継続して勉強しましょう。
4.勉強にお金をかけない
お金はなるべくかけたくないと考えるのは自然なことです。
しかし、合格率を高めるために必要最低限のお金はかけましょう。
不合格になったらその分の時間を無駄にすることになります。
また、お金はかけた分だけ後に引けなくなるので、合格するしかなくなり自身のモチベーション維持に繋げやすいです。
例えば、宅建に関する知識がほとんどない初学者の場合には、正しい知識を正しい解釈でインプットする必要があります。
まとめ

本記事では、宅建に宅建に受からない人の割合や特徴などをまとめました。
宅建に受かるためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 宅建にどんな問題が出るのか、出題傾向を把握する
- 過去問は目的をもって解く
- 勉強時間を確保する
- お金はかけるべきところにはかける
宅建は合格率が低く難易度が高いので、何度も落ちてしまうことは珍しくありません。
しかし、上記のポイントを押さえつつ、勉強の質を高めれば合格することは可能です。
仮に、宅建試験に何度も落ちてしまった場合には、勉強法が間違っているか勉強時間が不足しているかのいずれかが原因なので、まずは正しい学習法を確保するためにプロの宅建講師から学べる宅建通信講座を受講しましょう。
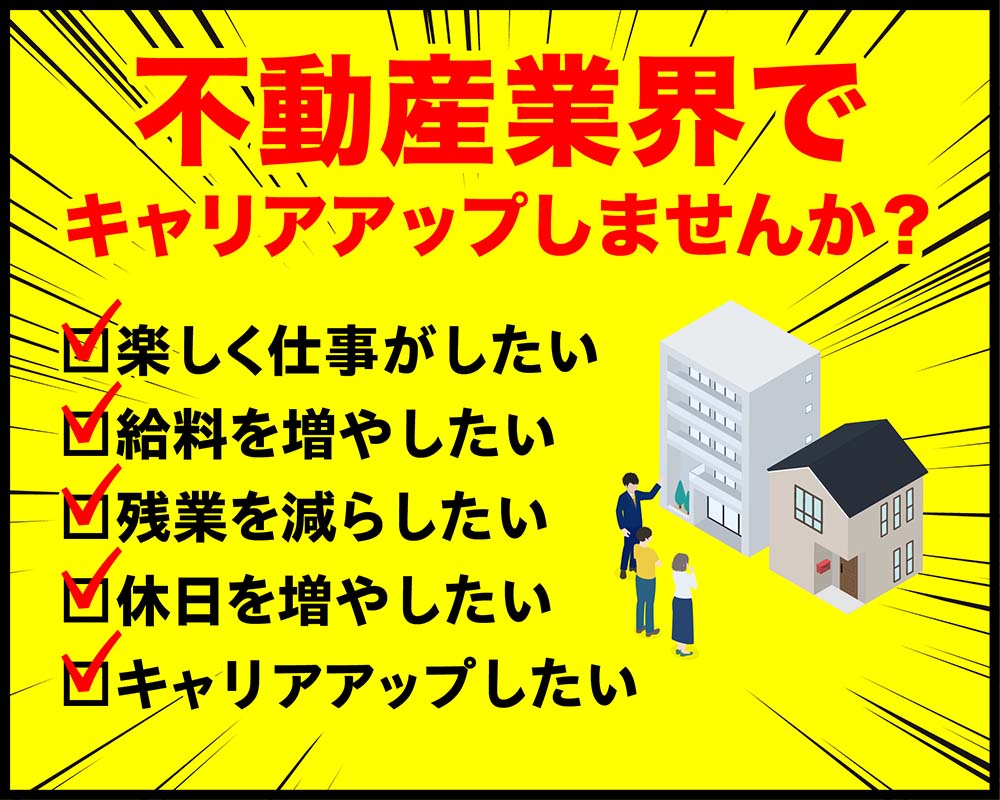
\ 積極採用中!/
最新記事 by ガースー (全て見る)
- 宅建試験2025年版!申し込み期間・方法・注意点まで完全ガイド - 2025年7月14日
- 宅建を復習する効率的な学習テクニック - 2024年3月25日
- 宅建の難易度は?過去10年間の推移を解説 - 2024年3月25日
- 宅建合格に必要な勉強時間が200時間〜300時間って本当? - 2024年3月25日