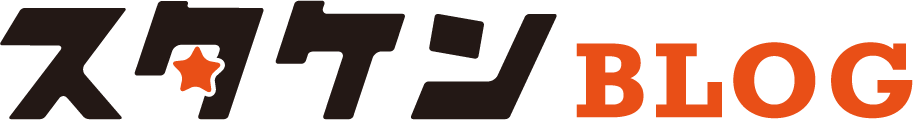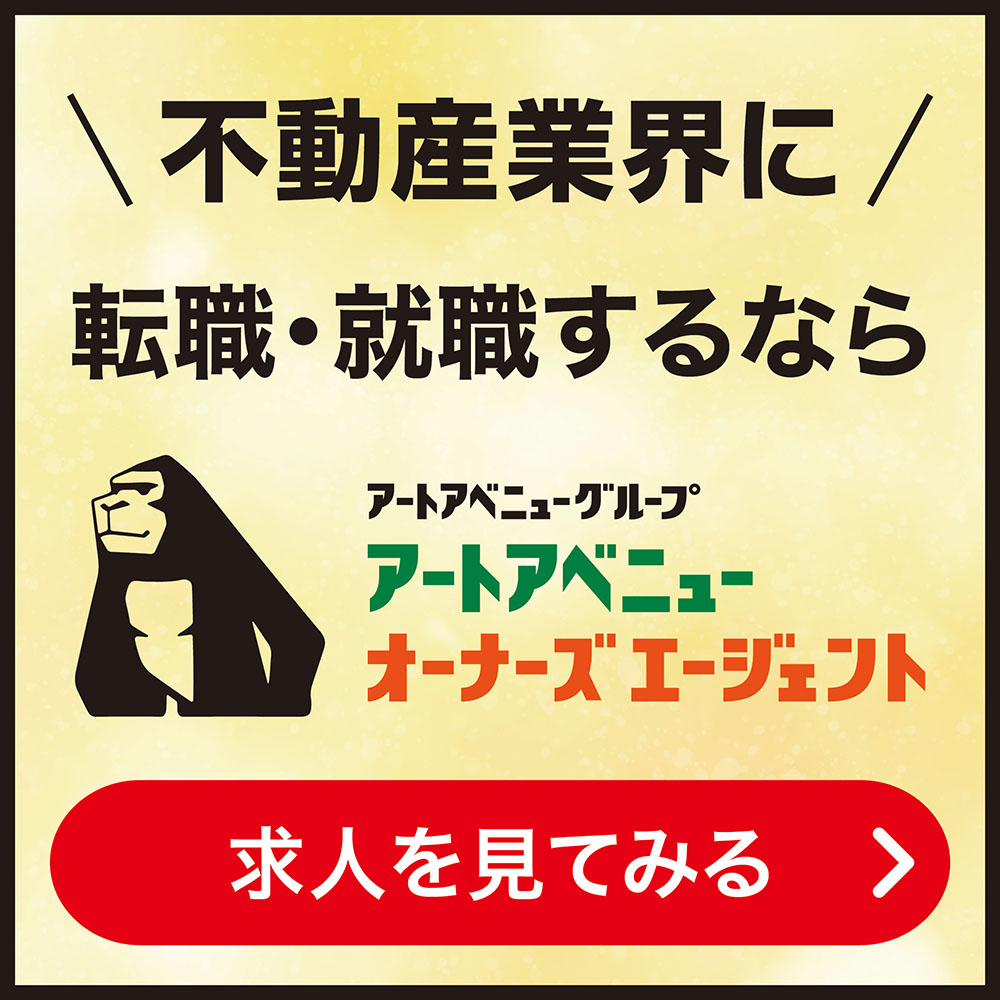数多くある資格試験の中で、 難易度が高いとされつつも人気の高い宅建資格。
宅建は「宅地建物取引士」という正式名称で、宅地建物取引業法で定められた国家資格です。
国家資格というだけあり、毎年の合格率は決して高いものではなく、独学で勉強する場合にはさらに難易度が高くなります。
これから宅建取得にむけて勉強していく方は、独学でも合格できるのかどうかが気になるところです。
そこで、今回は宅建試験の合格率や合格ライン、試験攻略法について詳しく解説します。
宅建の資格取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
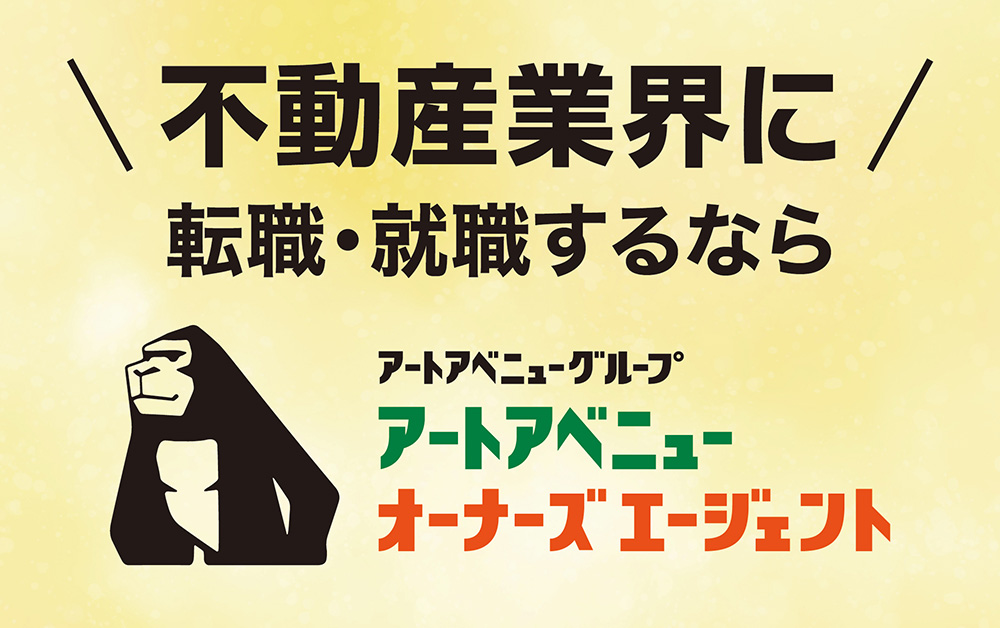
\ 積極採用中!/
この記事で学べること
宅建の合格率・合格ラインの推移

以下の表は、過去10年分の合格率・合格ラインの推移をまとめたものです。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格ライン(点) |
| 令和5年度 | 233,276人 | 40,025人 | 17.2% | 36点 |
| 令和4年度 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% | 36点 |
| 令和3年度(12月) | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% | 34点 |
| 令和3年度(10月) | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% | 34点 |
| 令和2年度(12月) | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% | 36点 |
| 令和2年度(10月) | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% | 38点 |
| 令和元年度 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% | 35点 |
| 平成30年度 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% | 37点 |
| 平成29年度 | 209,354人 | 32,644人 | 15.6% | 35点 |
| 平成28年度 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% | 35点 |
| 平成27年度 | 194,926人 | 30,028人 | 15.4% | 31点 |
| 平成26年度 | 192,029人 | 33,670人 | 17.5% | 32点 |
過去10年の宅建の合格率を見る限り、15〜17%の間を推移しているとわかります。
合格ライン(基準点)の変動は大きく、31〜38点と年度によってバラバラです。
出題される問題の内容や受験者のレベルによって異なりますが、37点以上取得しておくと、基本的に合格ラインに到達できると言えるでしょう。
また、受験者の数も年々増加傾向にあり、最新の令和5年度の試験では約23万人受験しています。
受験者全体のレベルも上がっているため、将来的に合格基準点が上がっていってもおかしくないでしょう。
宅建の試験方式

宅建は比較的難易度が高めな資格試験として認知されていますが、具体的な合格基準や合格ライン、合格率を知らない方は少なくありません。
そのため「合格基準」「合格ライン」「合格率」の3つを軸にして、宅建の試験方式を紹介します。
合格基準
宅建試験の合格ライン(基準点)は「相対評価方式」で決められています。「〇点取れば合格」と明確に定められているわけではなく、「上位〇%以内に限り合格できる」という形式の試験です。
宅建は明確な合格ラインが設けられていないため、例年の合格ラインを比較して「このくらいの点数を取っていれば間違いないだろう」と予測を立てて学習していく必要があります。
年度によっては例年よりレベルが上がる場合もあり、「予測よりも合格ラインが上回り、不合格になってしまった」というケースも少なくありません。
宅建試験の合格率を高めるには、過去問で合格最低点より2・3点余裕をもって取れるように、コツコツ学習を進める必要があります。
合格ライン
宅建試験の合格基準は、「相対評価方式」で決められています。
「100点中75点以上取れれば合格」とあらかじめ合格ラインが決められている「絶対評価方式」の資格試験もありますが、宅建試験は絶対評価方式の資格試験とは異なり、合格ラインが毎年変動しています。
過去10年分の推移を見てわかるように、宅建試験の合格点の変動は大きいものの合格率はほぼ一定なので、点数より合格率が参考になります。
目標にするのは「上位15%に入るようにすること」です。過去問や模試を解いた際には、合格点だけでなく合格率をより意識するようにしてみましょう。
合格率
宅建試験は、合格率15%前後を基準としているため、100人受験すると15人合格できます。上記の合格率を厳しいと捉えるか易しいと捉えるかは個人差がありますが、一般的には「そこそこ難しい」レベルと言われています。
数ある資格の中で10%台の合格率というのは、もちろん簡単に合格できるものではありません。しかし同じ国家資格で比較してみると、社労士や司法書士など10%にも満たない合格率の資格も存在しています。
そのため、簡単ではないものの、社会人として仕事をしながらでも学習時間を捻出して合格可能な資格であるといえるでしょう。
しかし、勉強に慣れていない方が、合格率15%前後の資格試験を独学合格するのは難しいので、スタケンの受講をおすすめします。
スタケンのサービス内容については「スタケンのサービス内容|合格圏内を突破する勉強法も徹底解説」の記事で紹介しているので、合格を勝ち取りたい方はぜひご覧ください。
宅建の合格率が低い理由

宅建の合格率が低い理由は、以下3つです。
- 試験範囲が広い
- 入社早々受験させられるケースが多い
- 受験資格に制限がなく誰でも受けられる
合格率が低い理由を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
試験範囲が広い
宅建の合格率が低い理由として、試験範囲が広いことが挙げられます。
宅建には、以下4つの科目があります。
- 権利関係(民法) 14点満点
- 宅建業法 20点満点
- 法令上の制限 8点満点
- 税その他 8点満点
宅建試験は、すべて合わせて合格点を取らなけらば資格を取得できません。
一方、同じ国家資格である税理士の場合は、科目ごとに合格・不合格が出て11科目のうち5科目合格すれば取得できます。
合格した科目は勉強する必要がないため、次の試験まで不合格だった科目を集中的に勉強可能です。
しかし、宅建試験はすべて合わせて合格点を取らなければいけないので、次の試験まですべての範囲をもう1度勉強する必要があります。
宅建試験は、全ての範囲を網羅的に学習した状態で試験に挑まなければいけないため、合格率が低くなっています。
入社早々受験させられるケースが多い
入社早々受験させられるケースが多い点も、宅建試験の合格率が低い理由の1つです。
他の資格試験の場合、受験者の方は基本的に試験内容をある程度学習した上で、本試験に挑みます。
一方、宅建試験の場合は、勤め先の上司やルールによって半強制的に受験させられるケースが多いです。
十分な勉強時間を取らないまま試験に挑んでいる方が多く、受験者全体のレベルが低くなっているため、合格率も低くなっています。
受験資格に制限がなく誰でも受けられる
宅建試験の合格率が低い理由として、受験資格に制限がなく誰でも受けられる点も挙げられます。
他の受験資格がある資格試験の場合、ある程度業界に関する知識や教養が身についている方のみ受験しています。
一方、宅建試験の場合は、受験資格がなく誰でも受けられる状態なので、「とりあえず受けてみよう」という方も多いです。
難易度の高い試験なので、ほとんど勉強していない方は点数が取れず、合格率が低くなっています。
宅建に合格するために必要な勉強時間

宅建の合格に必要な勉強時間は、200〜300時間です。
宅建試験の学習試験がない方や、法律・不動産関係の資格試験を受験したことがない方は、平均500時間ほど勉強するケースも多いです。
そのため、初学者の方が宅建試験を受ける場合、300〜350時間程度は学習時間を確保しなければいけません。
300〜350時間と聞くと、「そんな長い時間学習を継続できる自信がない…」という方も多いはずです。
学習時間の確保が難しい方や、勉強を継続できる自信がない方は、通信講座の利用がおすすめです。
通信講座を利用すると、プロから宅建試験合格に必要なノウハウを学べるだけでなく、自身のペースに合わせて学習を進められます。
合格率の低い宅建試験を攻略する方法

この項目では、合格率の低い宅建試験を攻略する方法を3つ紹介します。
- 独学で勉強する
- 通信講座で勉強する
- 通学制のスクールで勉強する
合格するための勉強方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
独学で勉強する
費用をかけずに合格を目指したい方は、独学で勉強する方法がおすすめです。
独学は、教材さえ購入すれば学習を進められるため、コストを抑えて資格取得を目指せます。
ただし、教材選びや学習計画など、全て自身で調べたり工夫したりしなければいけない点は、注意が必要です。
また、わからない箇所を誰かに質問できない点も、デメリットの1つです。
宅建試験は、不動産に関する専門用語が多く登場するため、初学者の方は理解するまでかなりの時間を要します。
宅建試験に独学で合格するには、勉強が得意な方や、過去に難関資格に独学で合格した経験がある方でなければ難しいでしょう。
なお、宅建試験の独学合格に必要なテキストの選び方については「宅建の独学におすすめのテキスト10選」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
通信講座で勉強する
効率良く合格を目指したい方は、通信講座で勉強する方法がおすすめです。
通信講座は、合格に必要なカリキュラムやテキストが用意されているため、独学のようにテキスト選びや学習スケジュールの管理に苦戦しません。
また、カリキュラムは基本的にオンラインで自身のペースに合わせて進められるため、忙しい方でも受講しやすいです。
自身で学習スケジュールを管理できない方や、プロ講師から自身のペースでノウハウを学びたい方は、通信講座を受講しましょう。
ただし、通信講座によっては学習サポートがなかったり、カリキュラムの内容が薄かったりする点は注意が必要です。
勉強のモチベーションを維持できる学習サポートや、本試験に出題される重要事項を中心に学習したい方は、スタケンの受講がおすすめです。
スタケンのサービス内容や受講するメリットについては、「スタケン®のサービス内容」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
通学制のスクールで勉強する
時間の融通が利きやすい方や、資金に余裕がある方は、通学制のスクールで勉強することをおすすめします。
通学制のスクールは、講師に直接質問できるだけでなく、周りの受講生と学習進捗を共有しながらモチベーションを維持することも可能です。
3つの学習方法の中で最も学習環境は良いですが、スクールごとに講義の時間が決まっているため、時間の融通が利きづらい点はデメリットです。
また、教室も場所が決まっているので、お住まいの地域によっては通学制を選択できない可能性もあります。
通学制のスクールを選択できない方は、前述した通信講座の利用がおすすめです。
合格率の低い宅建を取得するメリット

他の国家資格と比べると、宅建の難易度は低めです。しかし、難易度の低さが理由で人気が高いわけではなく、宅建の取得そのものに大きなメリットがあるため人気が高いです。
ここでは、宅建取得のメリットを3つ紹介します。
- 活躍の場が広がる
- ダブルライセンスの第一歩となる
- 独占業務ができる
活躍の場が広がる
宅建を取得するメリットとして、活躍の場が広がる点が挙げられます。
宅建を取得すると、不動産業界以外に、金融業界や一般企業でも重宝される人材となれます。
金融業界の場合、銀行・保険会社・証券会社など、宅建士の知識を求めている企業は多いです。
また、一般企業の場合は、自社が所有している不動産の管理や新店舗用の土地の取得など、宅建士が活躍できる場面は多々あります。
業界を問わず活躍の場を広げられるため、就活やキャリアアップにも活かせるでしょう。
ダブルライセンスの第一歩となる
ダブルライセンスの第一歩となる点も、宅建を取得するメリットの1つです。
宅建試験で学習した知識やノウハウは、他の資格取得を目指す際にも役立ちます。
例えば、マンション管理士試験の場合、宅建の学習範囲である民法や建物区分所有法が出題されます。
将来的に国家資格のダブルライセンスを目指している方は、まずは宅建の学習からおすすめします。
独占業務ができる
宅建を取得するメリットとして、独占業務ができることも挙げられます。
宅建士のみできる独占業務は、以下の通りです。
・重要事項の説明
・重要事項説明書への記名押印
・契約内容記載書面への記名押印
不動産は高額な物件のやり取りが多いため、宅建士が重要事項説明を行い、取引が適正に行われていることを伝えなければなりません。
また、宅建業を行う業者は、事務所で5人に1人以上の専任の宅建士を置かなければいけません。
例えば、従業員が13人の場合は3人以上の宅建士、19人の場合は4人以上の宅建士が必要となります。
会社の規模を拡大するほど宅建士が必要となるため、不動産業界では常に宅建士の存在が求められています。
宅建試験の合格率を他の資格と比較

この項目では、宅建試験の合格率を以下7つの資格と比較しながら解説します。
- ファイナンシャルプランナー
- 日商簿記
- 行政書士
- 不動産鑑定士
- マンション管理士
- 管理業務主任者
- 賃貸不動産経営管理士
他の資格と宅建試験の合格率を比較したい方は、ぜひ参考にしてください。
ファイナンシャルプランナーと合格率を比較
ファイナンシャルプランナーの合格率は、以下の通りです。
3級:60〜70%
2級:30〜40%
合格率を比較する限り、ファイナンシャルプランナーよりも宅建試験の方が難易度は低いと言えます。
ファイナンシャルプランナーの試験科目は6科目となっており、宅建試験よりも多いです。
しかし、学習する内容は保険や税金など日常生活に関連する内容ばかりなので、宅建試験よりも短い勉強時間で合格できるでしょう。
なお、宅建とファイナンシャルプランナーの難易度比較については「宅建とFPのどちらが使える?」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
日商簿記と合格率を比較
日商簿記の合格率は、以下の通りです。
3級:40〜50%
2級:20〜30%
合格率を比較する限り、日商簿記よりも宅建試験の方が難易度は高いと言えます。
日商簿記は、絶対評価を採用しており、試験の難易度に関わらず、本番試験で70点以上取ると合格となります。
試験形式で比較しても、相対評価を採用している宅建試験の方が合格は難しいと言えるでしょう。
なお、宅建と日商簿記の難易度比較については「宅建と簿記2級どちらを先に取るべき?」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
行政書士と合格率を比較
行政書士の合格率は、10%前後です。
全60問を3時間で解き、以下の合格条件を満たせば合格となります。
- 法令科目:122/244
- 一般知識等科目:24/56
- 全体:180/300※全ての条件を満たして合格
合格条件の点数は高くないものの、合格率は宅建試験よりも低いため、宅建試験以上に合格が難しい資格試験です。
なお、宅建と行政書士の難易度比較については「宅建と行政書士どちらがおすすめ?」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
不動産鑑定士と合格率を比較
不動産鑑定士の合格率は、33%前後です。
合格率を比較する限り、不動産鑑定士よりも宅建試験の方が難易度は高いと言えます。
不動産鑑定士の試験は、行政法規と鑑定理論の2科目が出題され、宅建を学習すると行政法規の学習範囲を一部カバーできます。
ただし、短答式試験に合格すると合格率14%の論文式試験が控えている点は注意が必要です。
マンション管理士と合格率を比較
マンション管理士の合格率は8%前後です。
合格率を比較する限り、マンション管理士よりも宅建試験の方が難易度は低いと言えます。
マンション管理士の試験は、民法や借地借家法など、宅建試験で学習した内容と被る部分が多いです。
しかし、宅建試験に比べて細かい内容を問われるため、より深く理解しなければ問題を解けません。
管理業務主任者と合格率を比較
管理業務主任者の合格率は、20%前後です。
合格率を比較する限り、管理業務主任者よりも宅建試験の方が難易度は高いと言えます。
管理業務主任者の試験は、前述したマンション管理士と内容は似ていますが、深い知識は問われません。
宅建取得後のダブルライセンスについて迷っている方は、管理業務主任者の資格がおすすめです。
賃貸不動産経営管理士と合格率を比較
賃貸不動産経営管理士の合格率は、30〜50%です。
合格率を比較する限り、賃貸不動産経営管理士よりも宅建試験の方が難易度は高いと言えます。
一部内容は宅建試験と被っているものの、建築構造や建築設備など、新しく学習しなければいけない単元も多いです。
宅建試験の合格率は他の資格試験と比較しても低い
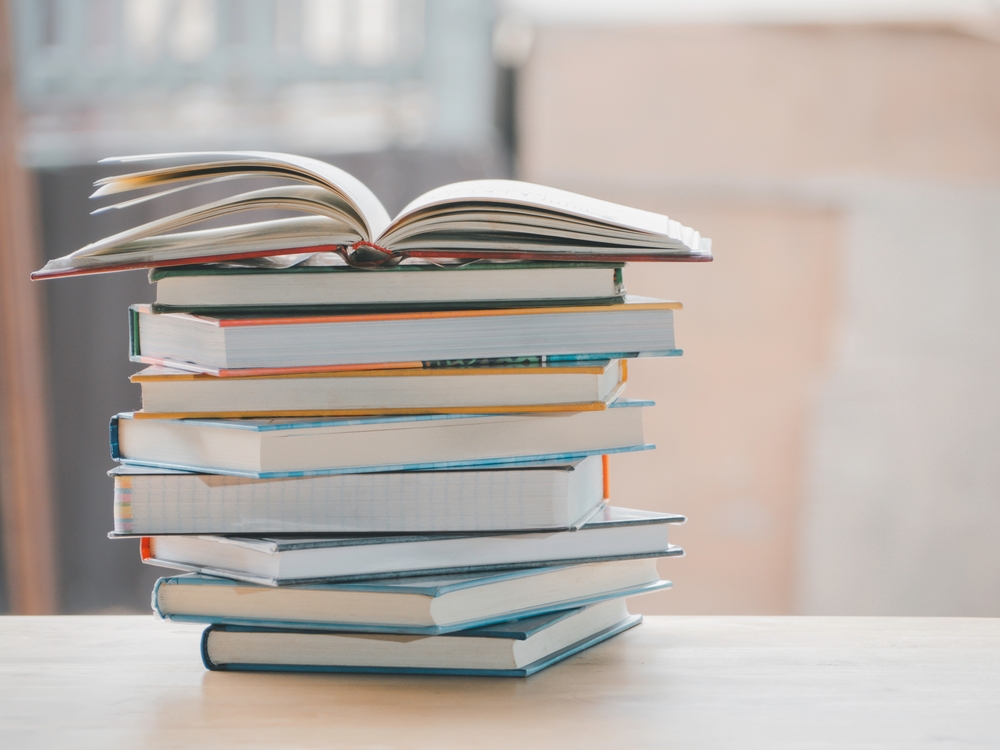
今回は、宅建試験の合格率や合格ライン、試験攻略法について詳しく解説しました。
宅建試験の合格率は、他の資格試験と比較しても低いため、国家資格の中でも難易度は高めです。
難易度が高い分、宅建取得をすることで得られるメリットはたくさんあります。
活躍の場を広げたい方や、就職・キャリアアップに役立つ資格を取得したい方は、宅建の合格を目指してみてはいかがでしょうか。
なお、宅建の学習方法がわからない方や、勉強を続けられる自信がない方は、スタケンの受講がおすすめです。
スタケンは、勉強のモチベーションを維持するためのサポートが手厚いので、初学者の方でも一発合格を目指せるはずです。
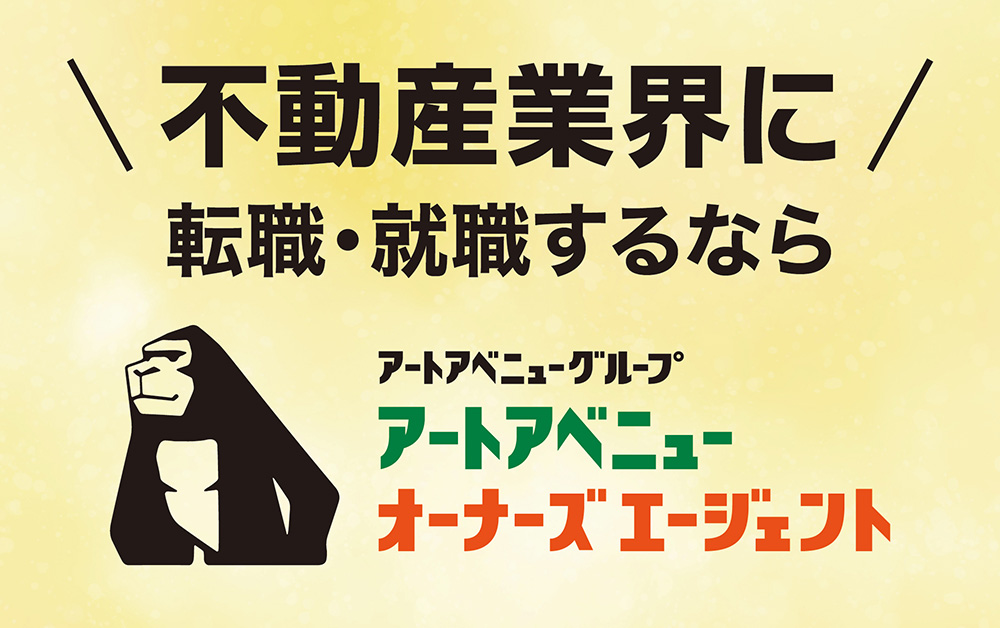
\ 積極採用中!/
最新記事 by ガースー (全て見る)
- 宅建を復習する効率的な学習テクニック - 2024年3月25日
- 宅建の難易度は?過去10年間の推移を解説 - 2024年3月25日
- 宅建合格に必要な勉強時間が200時間〜300時間って本当? - 2024年3月25日
- 2024年(令和6年度)宅建試験日&宅建申込スケジュールが決定! - 2024年3月21日