賃貸管理の可能性に、挑む。
当コラムでは「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」をオーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。
今回のテーマは「賃貸住宅管理適正化法」です。
賃貸住宅管理適正化法がついに成立

皆様、はじめまして。コンサルタントの山城と申します。
沖縄の賃貸管理会社に10年以上勤めた後、入居者対応や空室対策などの経験を糧に、現在はコンサルタントとして全国の賃貸管理会社に向けて情報発信および管理サポートを行っています。
今回のポイントは、2020年6月12日に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理適正化法)について。
ニュースなどで罰則ができることや登録の義務化といった言葉を聞いて、どう対応すればいいのか困っている方も多いと思います。
このコラムでは、法制化の内容や管理会社に与える影響、施行されるまでに備えておくべきことを一つひとつお伝えしていきます。
賃貸住宅管理適正化法とは?
そもそも賃貸住宅管理適正化法が成立した背景には、一部のサブリース業者による不誠実な業務実態が明るみになったという事情があります。
例えば、某不動産大手の「賃料減額取消訴訟」では、多くのオーナーに対して業績悪化を理由に賃料を減額させたサブリース業者が、業績を回復したにもかかわらず賃料を戻さなかったことが問題となり、100人を超える集団訴訟にまで発展しました。
また、悪名高い「かぼちゃの馬車」事件では、サブリース業者のスマートデイズが、破綻したビジネスモデルで強引な集客を行ない、最終的に約60億円もの巨額負債を抱えて倒産。残されたオーナーの多くが多額の損害を負う結果となりました。
こうした不動産会社とオーナーとのトラブルが相次いだことで、法制化の動きが加速し、ついに2020年6月に法案成立を見たわけです。
同法の目的はオーナーを守り、適正な賃貸管理を推進することでトラブルを未然に防ぐこと。
その実現に向け、国は管理会社に対して、以下の通り2つのルールを定めました。
- サブリース業者の禁止行為と罰則規定
- 管理業者の登録・業務に関する義務規定
さて、この2つ。いったいどのような内容なのでしょうか。
それぞれ要点を絞って解説していきます。
サブリース業者の禁止行為と罰則規定

度重なる不祥事ですっかりイメージダウンした「サブリース」。
業者とオーナー間で家賃保証などを原因としたトラブルが頻発し、社会問題化したことを受け、国はサブリースを規制するための【禁止行為】と【罰則】を新たに設けました。
対象は、「すべてのサブリース業者」。
また、建築会社やハウスメーカー、金融機関といった「サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)」も含まれます。
規定の内容は以下の通りです。
|
【禁止行為】
【罰則】
【施行時期】
|
①誇大広告等の禁止
マスターリース契約(特定賃貸借契約)を結びたいサブリース業者や勧誘者が、オーナーに対して契約条件について広告する際、
以下の事項について「著しく事実に相違する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をすることを禁じました。
- サブリース業者が支払うべき家賃
- 賃貸住宅の維持保全の実施方法
- マスターリース契約の解除に関する事項
- そのほか省令の定める事項
例えば、実際には契約内に保証賃料改定に関する規定が盛り込まれるにもかかわらず、「高い保証賃料を30年間変わらず払い続けます」と公告で謳い、オーナーを勧誘することは法に触れる行為となるわけです。
②不当な勧誘等の禁止
マスターリース契約を結ぶために、重要事項説明などでオーナーに対して客観的事実とは異なる内容を説明することも禁止となります。
例えば、賃料は市況によって変動するものですが、それを知らないオーナーに対して《不況になれば市場の賃料が下がる。賃料が下がれば保証賃料の減額もありうる》という客観的事実を告げずにマスターリース契約を結ぶといった場合は、この不当な勧誘等に当てはまるケースと言えるでしょう。
話を盛ってみたり、すぐにはバレない嘘を織り交ぜたりするトークは、昔なら営業手腕と言えたのかもしれません。しかし、甘言を弄してオーナーを丸め込む行為は今後ご法度というわけです。

とあるサブリース契約では、賃料を10年間にわたって保証すると説明したにもかかわらず、契約した数年後に著しい保証賃料の減額を迫ったり、減額を拒むと管理契約を解除したりするなど、業者の不誠実な実態が報じられました。
これはまさに「誇大広告」、そして「不当勧誘」の結果でしょう。
施行前とはいえ、サブリースに関する禁止行為と罰則が明文化された以上、管理会社に向けられるオーナーや世間の目は一層厳しくなることが容易に想像できます。
今のうちに会社内で周知を図り、営業手法や社員教育を見直すなど対策を講じた方がいいでしょう。
管理業者の登録・業務に関する義務規定

200戸以上を管理する事業者は登録対象に
法制化により、これまで任意登録だった【賃貸住宅管理業者登録制度】がついに義務化されることになりました。
賃貸住宅管理適正化法の施行後、管理業務を行なうためには国土交通大臣の登録が必要となります。
また、すでに任意登録されている場合であっても、新法施行に合わせて新たに登録する必要があります。
現在予定されている対象事業者は以下の通りです。(8月7日時点)
- 委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行なう事業を営もうとする者
- 管理戸数が一定規模以上※の事業者
※注意点※
- 現在のところ200戸以上と考えられているようです。
- 維持保全とは「住宅の居室やその他の部分について、点検、清掃などの維持に関する業務を行うとともに、必要な修繕を実施すること」。
- 金銭の管理は維持保全とセットになってはじめて賃貸住宅管理業と見なされます。そのため、金銭の管理のみを任されている物件は数に含まれません。
- 管理戸数が規定の数を下回る事業者でも登録可能。
- 登録の有効期間は5年、登録料は9万円と予定されています。
管理戸数の数え方で注意したいのは、対象物件についてオーナーとの契約の有無は問われないことです。
つまり、維持管理を媒介や取次、または代理で担当している場合、契約していないけれども維持管理を行なっている物件も登録の対象戸数にカウントされることになるのです。
ただ、法制化で義務化される以上、サービスで管理業務を行なっているのなら、これを機会にオーナーと管理契約の締結を検討したいですね。業務の適正化に繋がりますし、単純に利益も上がります。
登録業者として公的な立場を得るわけですから、業務報酬をしっかりと受け取れる体制を整えていきたいところです。
管理業務に関する義務
管理会社の登録義務の話をしましたが、登録業者には業務義務が課されるもの。
主に以下の4つの業務が義務化されることになります。
①業務管理者の配置
事務所ごとに「業務管理者」を配置しなければなりません。業務管理者とは、賃貸住宅管理業務において必要な知識および能力を有するもので、「宅地建物取引士」「賃貸不動産経営管理士」が想定されています。資格保有者は国の定める講習を経て、業務管理者に認定されます。
②管理受託契約締結前の重要事項の説明
オーナーに支払う賃料や、家賃の保証期間、サブリース契約解除の条件といった具体的な管理業務の内容・実施方法など契約における重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。
③財産の分別管理
管理する家賃などについては専用の保管口座を設けるといった対策を行い、自己の固有財産などと分けて管理しなければなりません。
④定期報告
業務の実施状況などについて、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告しなければなりません。
以上、登録・業務の義務規定について見てきました。
施行時期は少し先で、2021年6月ごろからと言われています。ただし、事業者登録の義務化は、さらに1年間(2022年6月ごろまで)の猶予が設けられる見通しです。
義務規定の内容は施行までにより具体化していくことになりますので、登録の可能性がある管理会社は動向を注視しつつ、義務化される業務を問題なく遂行できるよう準備を進めておきましょう。
急ぎ対応したい業務管理者の配置義務

業務管理者の配置義務で注目したいのが、「賃貸不動産経営管理士」の役割強化です。
賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸不動産の経営・管理に関するスペシャリストのこと。
今回の法制化で、宅地建物取引士と並び、業務管理者の要件を満たす資格となる見込みです。
業務管理者の確保は、管理会社にとって喫緊の課題と言えます。
もし業務管理者がいなかった場合、以下のことができなくなります。
- 貸主に対する賃貸住宅管理に向けた重要事項の説明および書面への記名・押印
- 貸主に対する賃貸住宅の管理受託と、契約書の記名・押印
つまり、業務管理者がいないと管理会社は全く仕事になりません。
そのため、宅地建物取引士に加え、業界では急速に賃貸不動産経営管理士の需要が高まると考えられます。
しかしながら、賃貸不動産経営管理士の資格試験が年々難化傾向にあることはご存知でしょうか。
合格率は2018年度の50.7%から、2019年度には36.8%に激減しています。
おそらく来年あたりには国家資格化が予想される賃貸不動産経営管理士。
今後さらに難しくなることが予想されますので、もし社員に資格取得を求めるなら、まだ国家資格になっていない2020年度こそ合格しやすい最後のチャンスと言えるでしょう。
僭越ながら、弊社では忙しい管理会社向けにWEB講座「スタケン賃貸不動産経営管理士」という教材をご用意しております。もしご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
いかがでしたでしょうか。
今回は賃貸住宅管理適正化法の知識をみなさんに共有いたしました。
新しい法律は経過とともに解釈なども変わってくる可能性もあるため、変化があれば随時更新していく予定です。
賃貸管理業界は日々めまぐるしい変化が起きています。現場で業務に励んでいると、仕事に集中するあまり、情報収集が疎かになってしまいがちです。
ただ、法制化の動きは私たちを待ってはくれません。
正しい知識を持って賃貸不動産の記念すべき節目を違反なく迎えられるよう、こうしたコラムを通して、今後も現場で役立つ知識を皆様にお伝えしていきたいと思います。

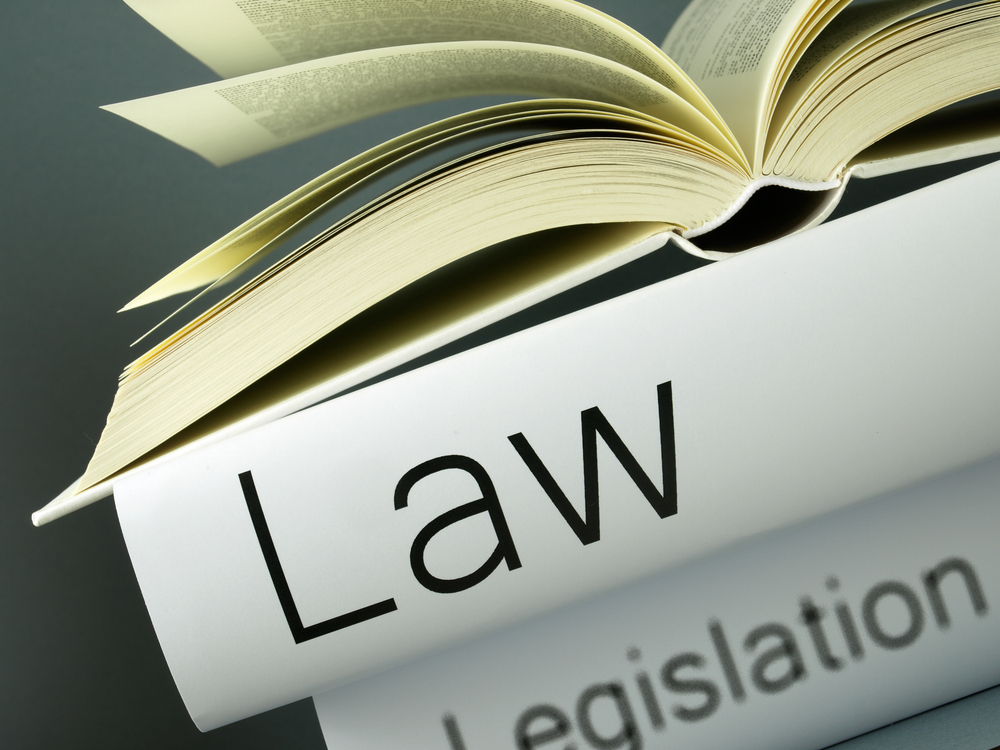








 相談してみる
相談してみる
