賃貸管理の可能性に、挑む。
当コラムでは、「賃貸管理ビジネスを成功に導くためのポイント」を、オーナーズエージェントのコンサルタントたちが分かりやすく解説します。
今回のテーマは「社員の知識習得促進」です。
社員の提案力高める学びの仕組みづくり
付加価値の提供には“知識”が必須
こんにちは、コンサルタントの高橋です。
管理受託営業を強化し、管理戸数が増えたにもかかわらず、思うように利益が出ない。そんな経営者様のお悩みを近頃よく耳にします。
内情をうかがうと、管理料の値下げ合戦や手間のかかる物件の受託、さらには物価高に伴う販管費の上昇が利益の圧迫に追い打ちをかけているようです。
いま賃貸管理会社には、効率化や経費削減だけでなく、利益の創出・確保を見据えた中長期的な事業戦略が求められています。状況の打開には、業務効率の改善のみならず、オーナーの抱える悩みに寄り添い、管理会社として付加価値を提供していく姿勢が欠かせません。
オーナーの課題を解決することは、新たな提案やサービスにつながり、管理料以外の収益を得るチャンスを生み出します。
ただし、その実現には社員一人ひとりが不動産全般に関する知識を習得し、適切なアドバイスや提案ができる力を備えることが欠かせません。
実は異なるオーナーの「期待と悩み」
なぜ社員の知識や提案力が必要かと言えば、オーナーと管理会社との間には、「期待」と「悩み」がすれ違うという大きな問題が横たわっているからです。
「賃貸管理オーナー動向データブック2024-2025」(全国賃貸住宅新聞社)に収録された「オーナーが管理会社を変更した理由」の調査結果を見てみると、ここでは一番に「空室が改善されない」が挙がり、「建物管理に不満」「入居者対応に不満」が続きます。これはつまり、オーナーが管理会社に対して「空室の改善」「建物維持管理」「入居者への適切な対応」といったことを「期待」していたということでしょう。当然、管理会社はこの期待に応えることを第一に考えるべきです。
一方で、同書の「家主の抱える悩み」の調査では、上位に「相続対策」「節税・経費削減」「遊休不動産の有効活用」などが挙げられています。利益創出を考えるのであれば、賃貸管理会社はこれらの悩みに貢献する必要があります。
しかし、前述の「管理会社への期待」を振り返ると…、残念なことに、管理会社は「空室」や「建物」の改善は期待されていても「相続」や「土地活用」の悩みの解決を“期待されていない”ことが分かります。
これらの相談は、管理会社より税理士や司法書士が優先され、物件の売却・購入といった重要な判断も、多くは売買の専門会社に先を越されているのが実情です。
このすれ違いの原因のひとつが、管理会社の知識量や信頼感です。オーナーは悩みを抱えながらも「相談相手がいない」「管理会社には荷が重いだろう」と考えているのです。
業績とやりがいを育む“学びの場”
このような状況を覆すには、各社員が不動産に関する深い知識を身につけるしかありません。とはいえ、業務に追われる中で「学び」の時間を確保するのは簡単ではなく、自主的に勉強を続けられる人も少数です。
そこで重要となるのが、会社が「学びの場」を用意する施策です。「勉強させるなんて時間も人も足りない」と感じるかもしれませんが、社員の成長なくして、会社の成長はありません。
学ぶ環境を少しずつでも整えることで、社員は知識と自信を得られ、日々の業務へのやりがいや前向きな姿勢も生まれます。そしてその積み重ねが、やがては組織全体の提案力や信頼につながり、会社の業績向上を叶えるのです。
これは決して特別な取り組みではなく、学びの場は日々の業務の中に少しずつ組み込むことができます。当社が実践している学びの場づくりをご紹介します。

任意参加の社内勉強会
強制ではなく、あえて「任意参加」の社内勉強会を開催しています。
事前に希望テーマを募り、関心のある回だけの参加も可能なスタイルです。無理に出席を求めないからこそ、勉強会には自然と意欲の高い社員が集まり、前向きで活発な意見が飛び交います。
いわゆる“2・6・2の法則”の通り、まずは積極層の2割を巻き込むことから始め、徐々に学びの輪を広げていくことを意識しています。
勉強会資料も肩肘張らず、必要最低限のシンプルな形で運用するのが継続の壁を越えるポイントです。
学びを応援する資格手当制度
宅建士や賃貸不動産経営管理士といった業務の必須資格にとどまらず、FP、不動産コンサルティングマスター、ホームインスペクターなど、幅広い資格の取得を推奨し、手当を支給しています。
この制度の目的は、もちろん価値ある提案のできる人材を育成することにありますが、社内に「常に学び続ける文化」を根づかせることも重要な目的のひとつ。
例えば宅建士を取得したあとも、別の資格手当があることで次にチャレンジしやすい環境が整い、継続的に知識を習得する意識が各社員に芽生えるのです。
社内実務テストの実施
オーナーに提案をする担当者には一定の知識が求められます。
そのため当社では、賃貸管理の基礎や不動産に関する時事情報、さらには実務で活用する投資分析などをテーマに、社内で定期的な実務テストを実施しています。
「社会人になってまでテストか…」と敬遠されるかもしれませんが、これは評価のためではなく、各自が自身の現在地を確認するためのもの。
実施を通じて、「意外と知らないことが多い」「後輩のほうが詳しいかもしれない」といった気づきが生まれ、自ら学ぶきっかけにもなっています。
知識の差がそのまま提案力の差につながるからこそ、現状を知り、学びの意識を持ち続けることが重要と考えます。
どの取り組みも目新しいものではありませんが、継続した知識習得には効果的です。
いずれにしても、人と時間というコストが必要となりますが、将来の成果と優秀な人材づくりの両方を見据えた投資として、今こそ学びの仕組みづくりを始めていきましょう。


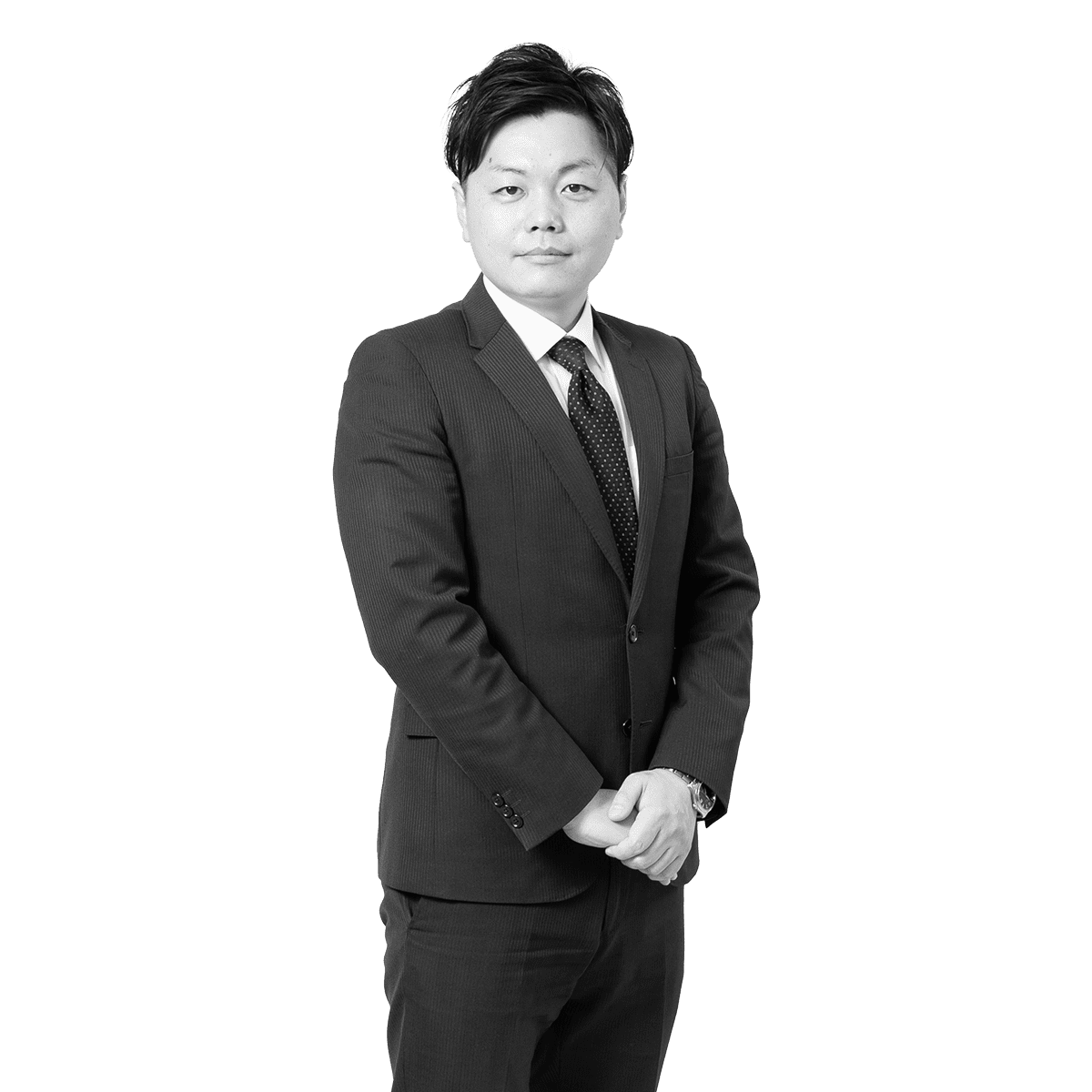











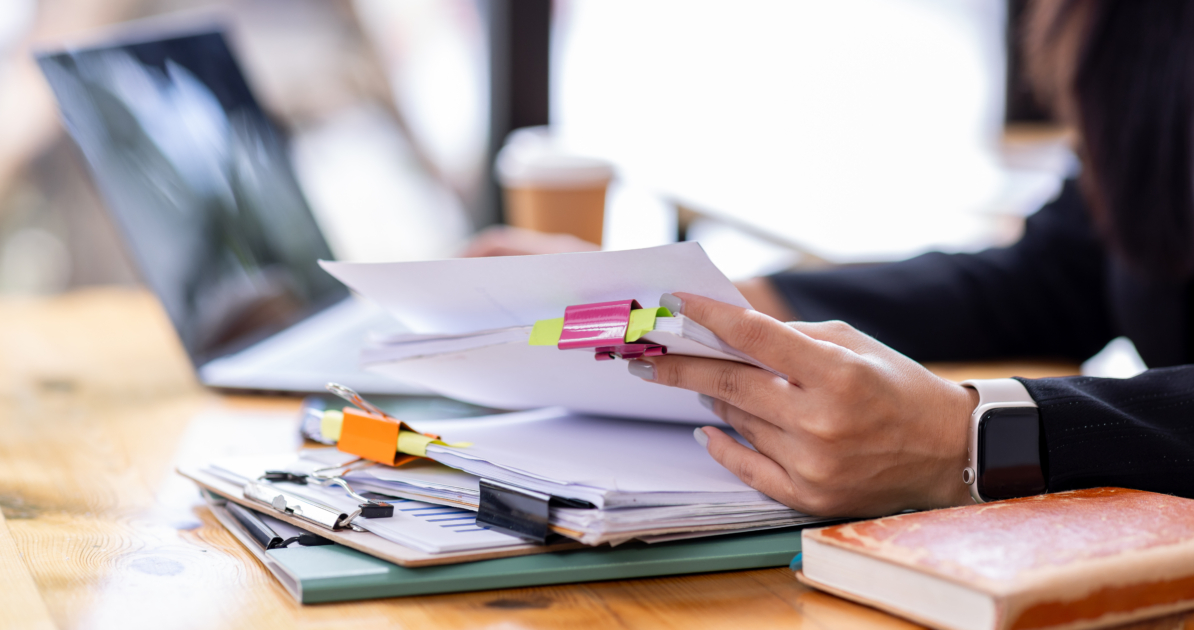

 相談してみる
相談してみる
