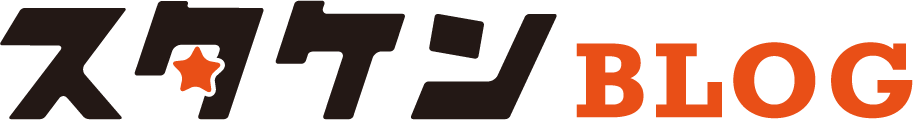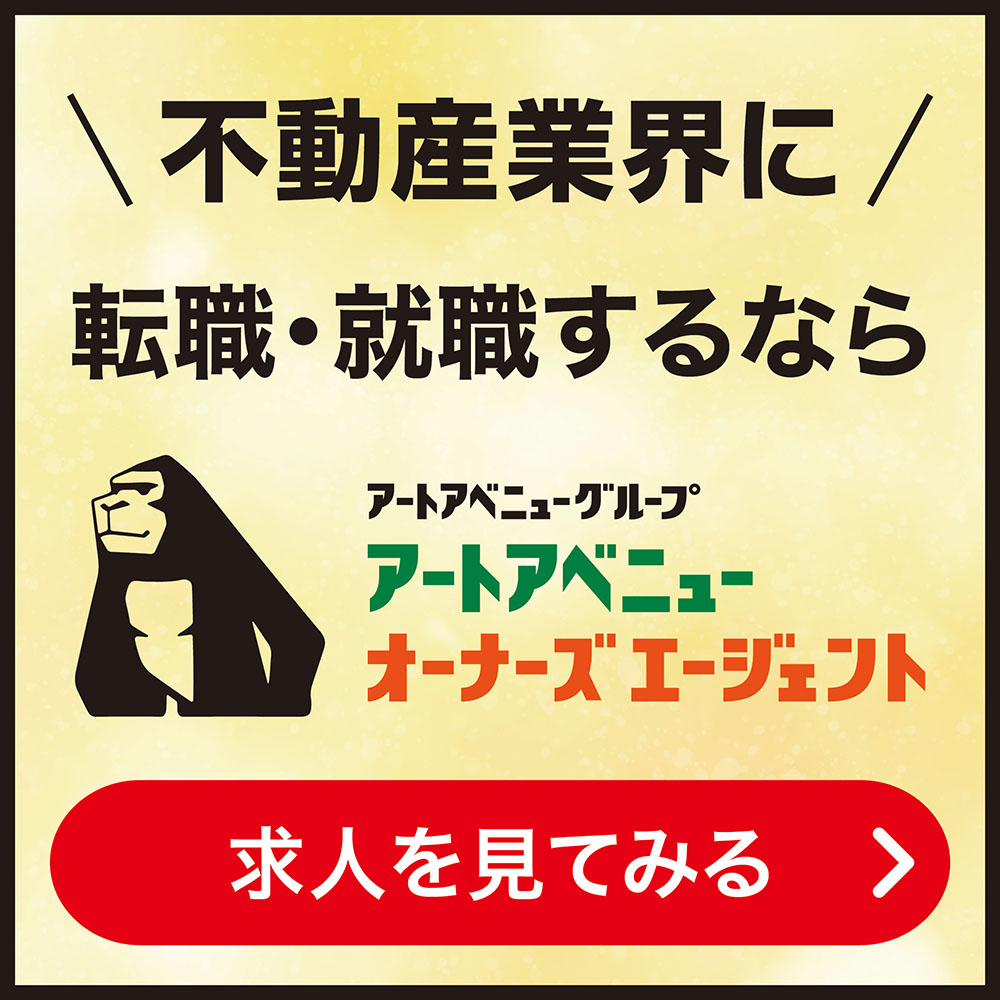宅建業法の中でも「 重要事項説明(35条書面)」は受験者にとって重要な項目ですが、記載事項が複雑で暗記量も増えるため、苦手とする方も多いでしょう。
しかし、宅建試験では毎年2問以上出されており、35条書面を避けて合格することはできません。
さらに、重要事項の説明は宅地建物取引士の独占業務となり、実務に携わる際にも必要な内容です。
この記事では、受験者にとって避けては通れない重要事項説明書(35条書面)について詳しく解説します。
- 重要事項説明とは、契約前に不動産の重要事項を宅地建物取引士が重要事項説明書を交付し説明することをいう
- 重要事項説明書の記載事項を網羅的に理解できる
- 不動産業界の就職・転職なら積極採用中のアートアベニューグループがおすすめ
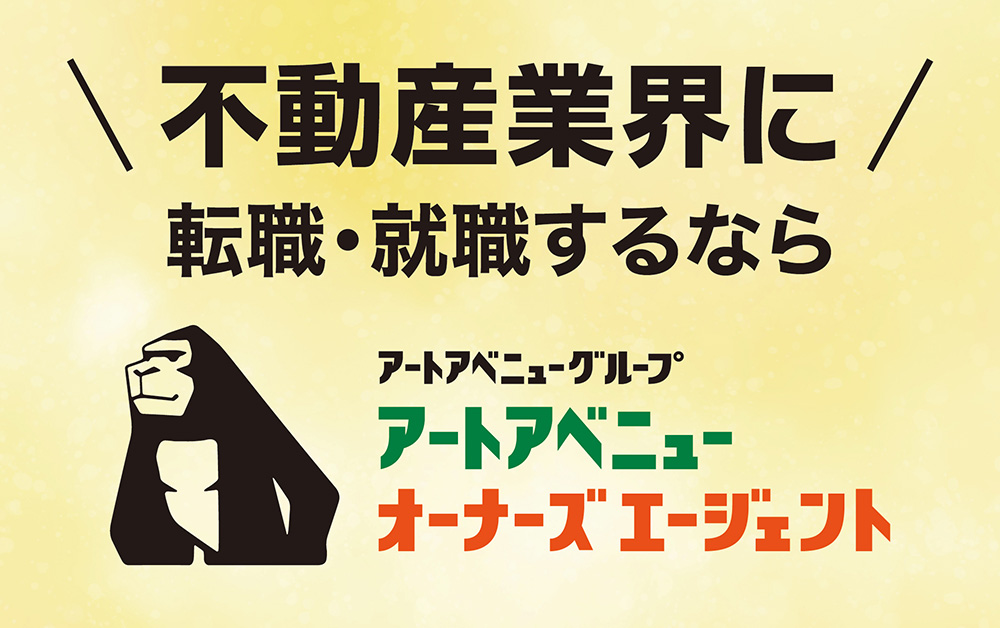
\ 積極採用中!/
この記事で学べること
重要事項説明とは

土地や建物の購入や賃借をしたことがない方にとって「 重要事項説明書(35条書面)」という言葉自体、聞き慣れないでしょう。
そもそも重要事項の説明とは、購入者や賃借人が損をしないよう、契約前に当該不動産の重要事項について宅地建物取引士が重要事項説明書を交付し説明することを言い、説明は義務付けられています。
重要事項説明を行う時期や場所などを分かりやすくまとめたので、整理しながら覚えましょう。
| 説明を行う者 | 宅地建物取引士(専任でなくても可) |
| 説明の時期 | 契約が成立するまで |
| 説明の方法 | 宅建士証提示・重要事項説明(35条書面)の交付をして行う |
| 説明する場所 | 定めなし(どこでも良い) |
| 説明する相手 | 宅建業者の相手方(買主や借主)
※売主や貸主に説明する必要はない |
説明の方法に「宅建士証提示」とありますが、これは、相手からの請求がなくとも宅建士証を提示する必要があります。
また、重要事項を説明する相手(宅建業者の相手方)が宅建業者である場合、重要事項を説明する必要はありませんが、35条書面の交付は省略できないことも覚えておきましょう。
重要事項説明書(35条書面)「宅建士の独占業務」
重要事項の説明は宅地建物取引士の独占業務です。重要事項説明の際に、宅建士は下記の4つの事務を必ず行います。
- 重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
- 重要事項説明書の交付
- 宅建士証の提示
- 重要事項の説明
1~4の事務は、宅建士であれば、専任の宅建士か否かを問わずに行うことができます。
ITによる重要事項説明(IT重説)
近年ではインターネットの普及や社会情勢により、パソコンやタブレットを使ったオンラインによる重要事項説明(IT重説)が可能になりました。
ただ、IT重説を行うためには以下の条件を満たす必要があります。
- 説明の事項を映像できちんと読むことができ、また音声のやり取りも双方が問題なく行えること。
- 重要事項説明書ならびに添付書類をあらかじめ、説明する相手方に送付しておくこと
- 映像及び音声の状況について、IT重説前に宅地建物取引士がきちんと確認すること
- 説明前に取引士証を提示し、相手方が画面上できちんと確認できたかどうか確認すること
ちなみに、令和3年3月30日より貸借の代理・媒介だけでなく売買・交換の際も、パソコンやタブレットを使ったオンラインによる重要事項説明(IT重説)が可能になりました。
つまり、IT重説は貸借・売買・交換、全ての取引で可能です。
重要事項説明書(35条書面)の記載事項

重要事項説明の記載事項は、宅地や建物の種類によっても「売買・交換」「貸借」といった取引内容によっても異なります。
最初は複雑に感じるかもしれませんが、それぞれを表にまとめたので、何度も見て整理しながら覚えましょう。
売買・交換・賃借共通の記載事項
| 記載事項
(宅地・建物の状況について) |
売買・交換 | 賃借 | ||
| 宅地 | 建物 | 宅地 | 建物 | |
| ①登記簿上の権利の種類・内容・名義人など(例:抵当権など) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②法令上の制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③私道に関する負担 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ④飲用水・電気・ガスなどの供給施設・排水施設の整備状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑤未完成物件における完成時の形状・構造 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥建物の状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要(既存建物) | × | 〇 | × | 〇 |
| ⑦建物の建築・点検記録および維持保全の状況に関する一定の書類の保存の状況 | × | 〇 | × | × |
| ⑧石綿(アスベスト)の使用有無 | × | 〇 | × | 〇 |
| ⑨造成宅地防災区域にあるときはその旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑩土砂災害警戒区域にあるときはその旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑪津波災害警戒区域にあるときはその旨 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑫水害ハザードマップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑬耐震診断を受けているときはその内容 | × | 〇 | × | 〇 |
| ⑭住宅性能評価 | × | 〇 | × | × |
| (取引条件について) | ||||
| ⑮代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の「額」「授受の目的」 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑯契約解除 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑰損害賠償額の予定など | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑱手付金などの保全措置の概要 | 〇 | 〇 | × | × |
| ⑲支払い金・預かり金を受領する場合の保全措置の概要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑳ローンの斡旋の内容およびローン不成立の場合の措置 | 〇 | 〇 | × | × |
| ㉑契約不適合責任に関する措置の概要 | 〇 | 〇 | × | × |
| ㉒割賦販売の場合、頭金及び割賦金の額・支払時期・方法 | 〇 | 〇 | × | × |
上記が売買・交換・賃借共通の記載事項です。
ここでは「宅地・建物の状況について」の①~⑭と「取引条件について」の⑮~㉑について重要なポイントを補足します。
②建物売買の代理・媒介を行う場合は、買主に用途制限や建蔽率などを説明する必要があります。しかし、建物賃借の代理・媒介を行う場合は、都市計画法などの説明は不要です。
③私道に関する負担がない場合にも「負担がない」旨を説明します。
④供給施設・排水施設が未整備であれば、今後の見通し、特別な負担の有無を説明します。
⑥建物調査上状況は、実施後1年を経過していないものに限り、結果の概要を説明します。
⑭住宅性能評価を受けた新築物件の場合のみ記載し、賃借なら不要です。
⑮手付金・敷金・保証金などが該当します。
㉑契約不適合責任に関する措置を講ずるか、及び措置を講ずる場合はその概要も説明事項です。
また、⑫の水害ハザードマップは、令和2年の法改正により追加された記載事項です。
令和3年度の宅建試験でも水害ハザードマップに関する問題が出されたので、土地や建物の売買・交換の際だけでなく、全ての取引に必要な記載事項であることを抑えておきましょう。
賃借のみ必要な記載事項
賃借の代理・媒介を行う場合、先ほど紹介した「売買・交換・賃借共通の記載事項」に「賃借のみ必要な記載事項」が追加されます。
| 記載事項 | 賃借 | |
| 宅地 | 建物 | |
| ①台所・浴室・便所等の整備状況 | × | 〇 |
| ②契約期間・契約更新に関する事項 | 〇 | 〇 |
| ③定期借地権に関する事項 | 〇 | × |
| ④定期建物賃貸借である場合、その旨 | × | 〇 |
| ⑤終身建物賃貸借である場合、その旨 | × | 〇 |
| ⑥用途制限・利用制限 | 〇 | 〇 |
| ⑦敷金など契約終了時における金銭の精算 | 〇 | 〇 |
| ⑧管理の委託を受けたもの氏名・住所 | 〇 | 〇 |
| ⑨契約終了時における宅地上の建物の取り壊し | 〇 | × |
上記の中でも、特に問われやすいのが①②⑦です。「記載事項が多すぎて辛い」という方は、まずは①②⑦を優先的に覚えましょう。
補足としては、
②契約期間・契約更新に関する事項は、「契約」という文字が入っていることから「契約書(37条書面)」への記載事項だと思われる方が多いです。
正しくは、35条書面の記載事項なので注意しましょう。
⑦敷金など金銭の精算に関する項目は、定まっていない場合にも、その旨を説明します。
区分所有建物のみ追加で説明する事項
建物の種類がマンションの場合にも「売買・交換・賃借共通の記載事項」に「区分所有建物のみ必要な記載事項」が追加されます。
| 記載事項 | 売買・交換 | 賃借 |
| ①敷地に関する権利の種類・内容 | 〇 | × |
| ②共用部分に関する規約の定め※ | 〇 | × |
| ③専有部分の用途その他の利用制限に関する規約※ | 〇 | 〇 |
| ④専用使用権の規約※ | 〇 | × |
| ⑤建物の計画的な維持修繕費用などの減免に関する規約※ | 〇 | × |
| ⑥計画的な維持修繕費用の規約・既に積み立てられている額※ | 〇 | × |
| ⑦通常の管理費用 | 〇 | × |
| ⑧管理委託を受けた者の氏名・住所 | 〇 | 〇 |
| ⑨建物の維持修繕の実施状況 | 〇 | × |
上記の記載事項の中でも、以下の3点については出題されることが多いです。
- 専有部分の用途その他の利用制限に関する規約
- 専用使用権の規約
- 管理委託を受けた者の氏名・住所
また、②③④⑤⑥の※印が付いている事項に関しては、規約が「案」である場合にも説明する必要があります。
まとめ

- 重要事項の説明は、宅建士が35条書面を交付し行う。
- 令和3年3月30日より、IT重説は貸借の代理・媒介だけでなく、売買・交換の際も可能。
- 35条書面の記載事項は、共通の記載事項と賃借、区分所有建物の際の追加事項を分けて覚える。
重要事項説明書(35条書面)は、宅建の試験でも毎年2問以上出される重要な項目です。
暗記しなければならない項目が増えるため「苦手」とする方も多いですが、全て暗記しようと思わず、試験で問われやすい項目を優先的に抑えて学習を進めていくと良いでしょう。
この記事で紹介した、記載事項の表を参考にしながら重要事項説明の理解を深めてくださいね。
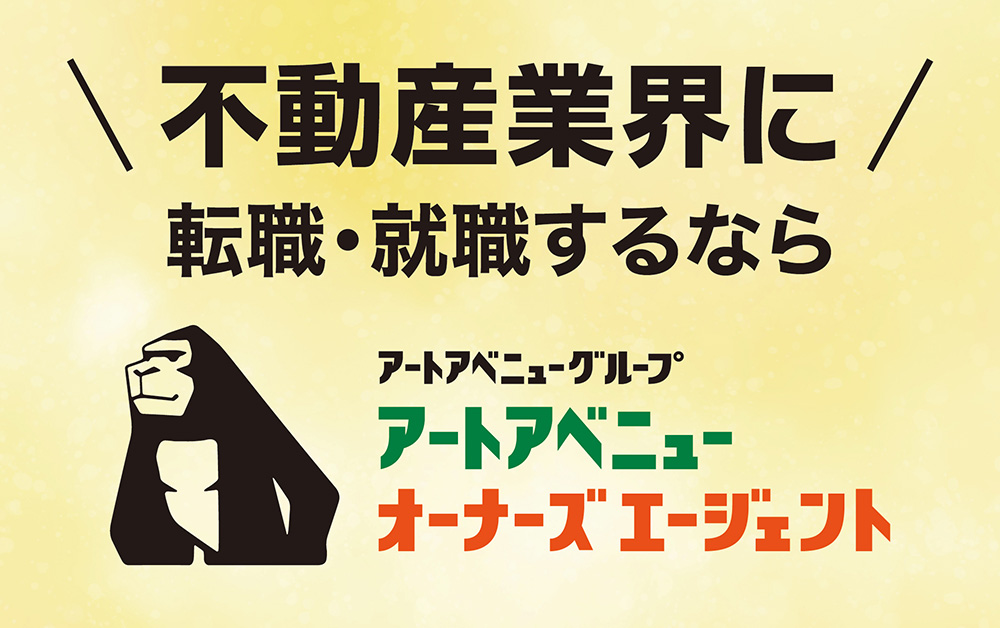
\ 積極採用中!/
最新記事 by ガースー (全て見る)
- 宅建を復習する効率的な学習テクニック - 2024年3月25日
- 宅建の難易度は?過去10年間の推移を解説 - 2024年3月25日
- 宅建合格に必要な勉強時間が200時間〜300時間って本当? - 2024年3月25日
- 2024年(令和6年度)宅建試験日&宅建申込スケジュールが決定! - 2024年3月21日