駐輪場は整備・美観維持・利便性の三拍子をそろえて
自転車大国日本 賃貸物件に駐輪場はマスト
オーナー提案のトークに役立つ小ネタ集「空室対策100選コラム」
今回、注目する空室対策は「駐輪場整備」です。
免許がなくとも子供から高齢者まで幅広い年代で利用できる交通手段・自転車。
日本における平均保有台数は1.03台/世帯、国内での総保有台数は推計5,700万台を超えます(自転車産業振興協会・2021年調査より)。
当然、賃貸住宅でも自転車の利用者は多く、駐輪場を使いたいというニーズは少なくありません。だからこそ、駐輪場がきちんと整備されていない物件では、さまざまな問題が発生する可能性があります。
例えば、内見の場面。駐輪場の見た目や環境が悪く、「ここには停めたくない」「使いたくない」と思わせてしまう物件に、自転車ユーザーは寄り付きません。
また、自転車ユーザーに限らず、駐輪場の状態は建物全体の管理品質を測るポイントの一つでもあるため、整備状況の悪い駐輪場は内見者に悪い印象を与え、入居付けにも影響を及ぼします。
さらに、駐輪場の環境が劣悪であれば入居者からも不満の声が。入居者満足度が低下して退去リスクが高まるだけではなく、管理上の手間も増えることでしょう。
こうしたリスクを防ぐためにも、荒れた駐輪場は早めの整備が大切。管理会社として、オーナー様に積極的に整備を提案していくことが肝心です。
放置自転車は今すぐ撤去 美観維持に努める

駐輪場整備に着手するなら、まず「放置自転車」の撤去から始めましょう。処分までの一般的な流れは次の通りです。
①入居者への通知
「○月○日までに移動がない場合は撤去します」等を明記した張り紙や通知文で各戸へ告知する。
②撤去・保管
所有者が確認できなかった自転車を物件から撤去し、一定期間(2週間~1ヶ月程度)保管。
③最終処分
所有者からの申し出がなければ業者へ依頼して廃棄またはリサイクル処理を実施。
実務としては、管理会社が①まで行い、②以降は専門業者に依頼するケースが多いでしょう。通知に際しては、注意点が2つあります。
1つ目は、「十分な期限を設ける」こと。撤去後に「撤去されるなんて聞いていない」「返してほしい」と主張されることを防ぐため、1ヶ月程度の猶予を設けておきましょう。
2つ目は、「通知方法への配慮」。特に、自転車の車体を汚したり傷付けたりするとクレームにつながるため、掲示や貼付の仕方には細心の注意を払いましょう。
また、長期の出張や旅行などで不在にしている入居者は張り紙に気付けません。撤去の告知をSMSで入居者へ一斉送信するなどの工夫があれば、無用なトラブルを避けることができます。
放置自転車に気付ける仕組み
このように、撤去や処分には時間も手間もかかるため、管理会社としては早期に放置自転車に気付き、発生させない仕組みを作ることが重要です。
王道の対策としては以下のような方法があります。
駐輪許可シールの配布
自転車の所有者(入居者)の情報と紐づけた駐輪許可シールを作成し、車体に貼付してもらいましょう。このとき、車種や色、防犯登録番号を申告してもらうと照合が楽になりますので、情報が管理できるのであれば検討してみてください。
また、シールを有料配布したり駐輪場代を設定すると、入居者間での監視効果や管理会社への相談・報告も期待できます。
退去時のルール化
登録者が退去する際には、自転車を新居へ持ち出すことを徹底させましょう。退去後、放置が発覚した場合は、処分費や送料を負担しなければならないなどの規約を定めておくと安心です。
こうしたルールを敷くことで、放置自転車の発生を抑え、所有者不明の車体も特定しやすくなります。
駐輪場の美観維持もポイント
放置自転車だけではなく、駐輪場そのものの美観にも意識を向けましょう。
コンクリートに苔が生えていれば高圧洗浄し、屋根に穴が開いているなどの不具合があれば適宜修理するなど、細やかなメンテナンスを心がけましょう。
また、駐輪状況が乱雑になっている場合は、原因に応じた対策を講じましょう。
スペース不足
駐輪スペースの拡張や新設を検討。敷地が限られている場合は、空いている駐車場区画を転用する方法もあります。物件のエリアの実態を踏まえた提案を行いましょう。
駐輪の乱れ
乱雑に駐輪している状態であるならば、ラックの設置を検討しましょう。しかし、こちらもある程度の敷地を必要とします。二段式・縦置き型・斜め置きなどの省スペース型のラックのほか、後述する電動アシスト自転車も停めやすい駐輪場であると入居者の不満も溜まりません。
整備・美観・利便性の3つのポイントをしっかり押さえて、オーナー様へ提案してみましょう。
人気の電動アシスト自転車 エリア分けで安全に駐輪
この10年ほどで電動アシスト自転車を選ぶ人は一気に増加しました。
経済産業省による自転車販売台数の資料によれば、電動アシスト自転車が自転車販売台数全体に占める割合は、2010年が約1/7だったのに対し、2020年になると全体の約1/2まで拡大。通勤や通学、子供の送り迎え、買い物といった日常の移動で、もはや欠かせない存在になりつつあります。
その一方で、駐輪場では意外に扱いづらい一面もあります。
電動アシスト自転車は、タイヤが太くてラックの幅に合わない、車体が20キログラムを超えるものもあり重くて持ち上げにくいなどの特徴があり、特にラック式の駐輪場では不都合が起こりやすいのです。
この課題を解決するには、ママチャリやシティーサイクルなどの軽快車向けのラック式とはまた別に、原付バイクと同じように白線で区切った平置きスペースを用意するやり方などが考えられます。
利用する自転車の種類で駐輪エリアを分けることで、安全性や利便性が確保しやすくなるでしょう。
プラスαのアイデアを スポーツバイクユーザーを取り込む

ロードバイクやクロスバイクなど、高価なスポーツバイクを趣味で所有する人も増えてきました。こうしたユーザーは、盗難や劣化防止の観点から、屋外や共用の駐輪場に停めることをためらう傾向にあります。
この対策には、自転車を収納したり飾ったりできる設備を室内に導入する、という方法も。さらに「自転車好きのためのコンセプトルーム」として募集を行えば競合物件との差別化にもつながります。
特に1階住戸は自転車の持ち込みがしやすく、この取り組みとの相性は抜群。壁面にスポーツバイク用のディスプレイラックを設け、簡単な飾り棚を取り付ける程度のプチリノベーションでも、趣味人に刺さる部屋づくりができるでしょう。
結果として付加価値がついて賃料アップも期待できるかもしれません。
まとめ
「たかが駐輪場」と思われがちですが、実際には物件の印象や入居者満足度を大きく左右するもの。日常的に使われる場所だからこそ、整備に手を抜くことはできませんし、ちょっとした改善が入居者の満足度向上に一役買います。
また、街を見ればシェアサイクルも広がり、自転車はますます生活に身近な存在となっています。物件の立地によっては、一歩踏み込んだ「シェアサイクルポートを誘致する」という選択肢も検討できるでしょう。
シェアサイクルとなると、駐輪場整備に比べてずいぶん思い切った施策に見えますが、実は結局、両者の効果は「入居者に快適な自転車利用環境を提供する」という同じもの。物件に何か付加価値を持たせたい、と考えているオーナー様がいらっしゃるならば、駐輪場整備と合わせて提案してみてはいかがでしょうか。
すぐ提案、チャンスを逃さない営業必携ツール
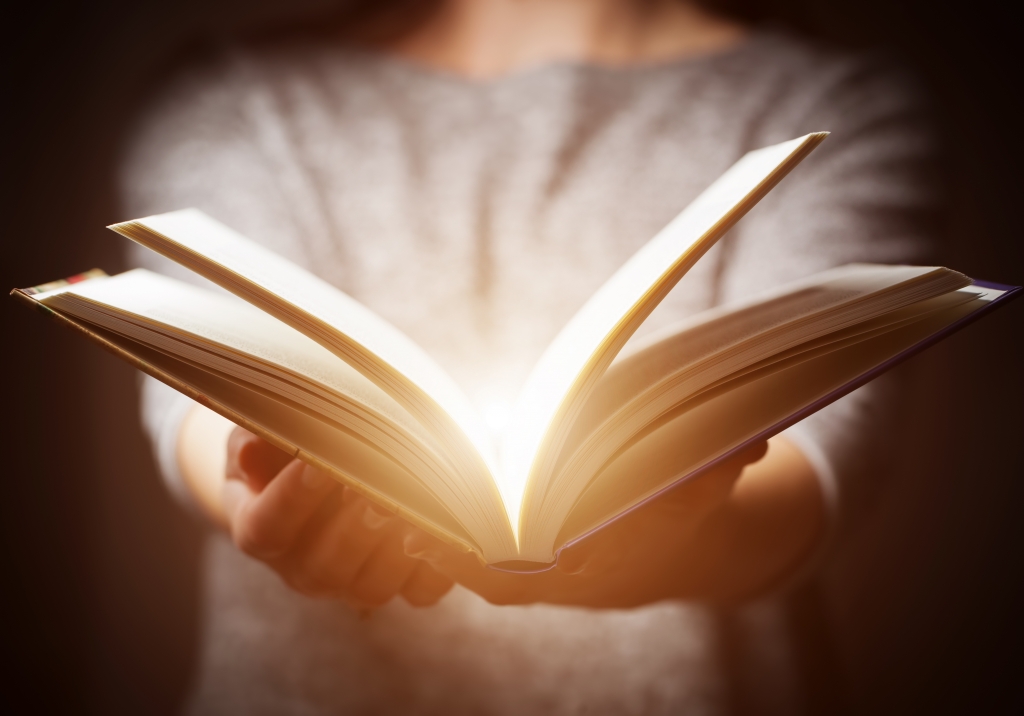
書籍『空室対策100選』発売中!
オーナーズエージェントでは、空室対策アイデアを100個つめ込んだハンドブック『空室対策100選』を好評発売中です。
営業社員に1冊持たせておくだけで、空室対策提案の採用率がぐんと高まります。オーナー提案ツールとして、この機会にぜひお役立てください。
●「駐輪場整備」の掲載ページ(サンプル)











 相談してみる
相談してみる
