置き場所を求めるバイクユーザー。希少性と快適性で差別化
都市部ほど駐輪スペース不足 バイク駐輪が空室対策に
オーナー提案のトークに役立つ小ネタ集「空室対策100選コラム」
今回、注目する空室対策は「バイク置き場新設」です。
コロナ禍以降、バイクの需要は増加傾向にあります。一般社団法人日本自動車工業会が実施した「2023年度二輪車市場動向調査」によると、2015年以降30万台水準だった二輪車需要台数は、2021年度以降40万台を突破。さらに、買い増しや新規購入もやや増加し、市場は上向きになっています。
また、同調査ではアンケート項目に「二輪車の駐車問題」も盛り込んでおり、これによると、「自宅周辺などで駐車に困った経験」がある人は全体の37%、東京23区では67%に達しています。
バイクユーザーにとって都市部ほど日常生活における駐輪スペース不足が深刻であることが分かるデータです。
こうした背景を考えると、「バイク駐輪が可能な賃貸物件」は、ただそれだけで希少性が高く、競合物件との差別化につながる可能性があります。
バイク駐輪場の新設・整備や、敷地内へのバイクの駐輪許可を出すことは、駐輪場代や家賃増額も期待できる、十分に検討価値がある空室対策でしょう。
バイク駐輪場を整備するための3つの提案
バイク置き場の整備にあたっては、敷地の広さやターゲットに応じて、次のような方法が検討できます。
■白線で区切った駐輪場
バイク駐輪場は、敷地内の地面に白線を引いて区分けするだけで設置可能です。
ただし、地面はできるだけアスファルトやコンクリートで舗装を。地面が柔らかいとスタンドが重さで沈んでしまい、バイクが倒れやすくなってしまいます。また、バイク同士の接触や転倒を防ぐため、区画の間隔は広めに取りましょう。
なお、車体を雨から守ることのできる「屋根」がついていると、バイクユーザーに「ここなら停めてもいいな」と思ってもらいやすくなります。舗装が必要な際などは必ずセットで提案しましょう。

■バイクガレージ設置
コンテナ型などのバイク用の「ガレージ」を購入・レンタルして、敷地内に設置します。
カスタムやメンテナンスも可能なプライベート空間は、こだわりのバイクを所有している方にとって夢のような施設。大切なバイクが盗まれたりしないよう、ガレージを見守るかたちで防犯カメラを設置するなど、セキュリティ面を強化すると訴求力がさらに高まります。
当然ながら、白線を引く方法の何倍もの面積を要するため、敷地内に設置できる数は限られます。また、「ガレージを借りたい!」というほど情熱的な方は少数派のため、設置数は市場のニーズをよく考えて決めましょう。
ちなみに、ガレージとなるとその希少性から、入居者だけでなく周辺住民からの契約申し込みが入ることがあります。
■近隣の遊休地を活用
敷地内に設置できない場合は、「別の土地」にバイク駐輪場を整備するのも手です。
オーナーが近隣で月極駐車場も経営しているならその一角に、あるいは別の所有アパートの駐輪場、場合によっては活用のアテがなく遊ばせている土地なども候補になるでしょう。中型~大型のバイクは、自転車よりも車に近い感覚で所有されているため、徒歩1~2分の距離感であれば、敷地外のバイク駐輪場まで歩くことになったとしても許容されます。
例えば、線路脇にある住宅にしづらい不整形地などは、実は騒音が気になりにくい点で有利であり、バイク駐輪場としての活用が狙い目です。
そして、駐輪場は単に停められるだけではなく、安心・快適に利用できる環境づくりが重要です。設備の充実度に応じて利用料を上げていくことも可能なため、バイクユーザーの利便性を考えたうえで、入居者満足度向上と家賃収入増の両方を叶えましょう。
なお、地域差はありますが、白線区切りや屋根付きバイク駐輪場の利用料目安は月3,000円~4,000円程度、バイク用ガレージは希少性から高めの賃料で貸し出すことができ、広さに応じて月8,000円~15,000円程度の収入が期待できます。
避けては通れない騒音問題。ルール作りは念入りに
その希少性から集客が見込める一方で、世間にバイク置き場が少ないことには理由があります。
その一つが、「騒音」の問題。バイクのエンジン音やアクセル音は、バイクに理解のない方には「騒音」として捉えられがちです。
近隣住民からクレームが頻繁に寄せられることになっては、オーナーも肩身が狭くなるうえ、管理会社の負担も増えることとなり、さらにはバイク所有者の解約・退去にもつながってしまいます。
バイク置き場を新設する際は、トラブルを未然に防ぐためにも、管理会社が以下のようなルールの設定・運用を主導しましょう。
・停められるバイクの排気量等の制限(中型(400cc)まで、改造車不可など)
・騒音発生行為の制限(長時間のアイドリング禁止など)
・通常使用時の特別な制限(○○地点までは車体を押して移動、敷地内での早朝・深夜のエンジン始動禁止など)
排気量等の制限は、募集時からきちんと公開し、バイクユーザーとの認識の相違が起こらないよう配慮します。また、契約書等にも騒音行為の禁止と合わせて盛り込めるとよいでしょう。
通常使用時の制限は、バイクユーザーにも負担となるため、実際に近隣とのトラブルが発生したあとでの対策候補です。
こうしたルールがあることは、近隣住民のクレームからバイクユーザー本人を守ることにもつながります。
マナー啓発と合わせてバイクユーザーにはルール順守の意義を丁寧に説明し、トラブルの起こりにくいバイク駐輪場運用を目指しましょう。
不利な立地でも戦える ガレージハウスという選択肢

もしも新築や建て替えのタイミングであれば、思い切ってバイク用のガレージハウス(ビルトインガレージ)を企画するのも一案です。
ガレージハウスは、駅から遠い・線路や幹線道路が近くうるさいなどの不利な立地であっても需要を掘り起こせる可能性があります。
しかし、ガレージハウスは単にバイクを格納する場所ではなく、「バイクを居住空間に組み込んだ」部屋づくりが求められます。バイクユーザーにとって必要なものはなにか、何が喜ばれるのかをしっかり分析しなければ入居が決まりません。
一般的なガレージハウスは、1階がガレージ・2階を居室にする作りがよく見られます。企画する際は、このガレージ部分へ置ける車種や台数、周辺設備などをイメージしたうえでスペースを算出する必要があります。
台数にもよりますが、中型~大型バイクを置くのであればガレージ部分は少なくとも4畳くらいのスペースを確保した方が安心です。メンテナンスやカスタマイズができる広さを確保するのであれば、6畳はほしいところでしょう。
さらに、ガレージ内でエンジンをかける時を考えて、防音・防振構造にしたり、排気ガスが充満しないよう換気口を付けたりといった工夫が求められるでしょう。また、安全な保管のために、シャッターを鍵付きにするほか、防犯カメラや人感センサーの設置などの防犯対策も検討しましょう。
そして、ガレージハウスで愛車と過ごす生活は、バイクユーザーにとってあこがれのライフスタイルです。
いつでも愛車を眺められられるように、ガレージの隣にリビングを配置して大きなガラス窓を設置したり、ガレージ内にエアコン・流し台・コンセント・収納ラックなどを設置して快適なメンテナンスができる空間をつくるなど、遊び心と機能性を備えた構造を考えましょう。
騒音や立地の面でハードルもあるバイク駐輪場ですが、管理会社からの提案やルール策定など、ソフト面からのアプローチによって実現が可能になる場合もあります。
オーナーの希望が望める・対象物件への設置が見込める場合には、管理会社が運営面をサポートしつつ、需要にマッチした、希少性の高い設備を備えた駐輪場となるよう提案をし、内見に来たバイクユーザーの心を掴めるような物件づくりを目指しましょう。
すぐ提案、チャンスを逃さない営業必携ツール
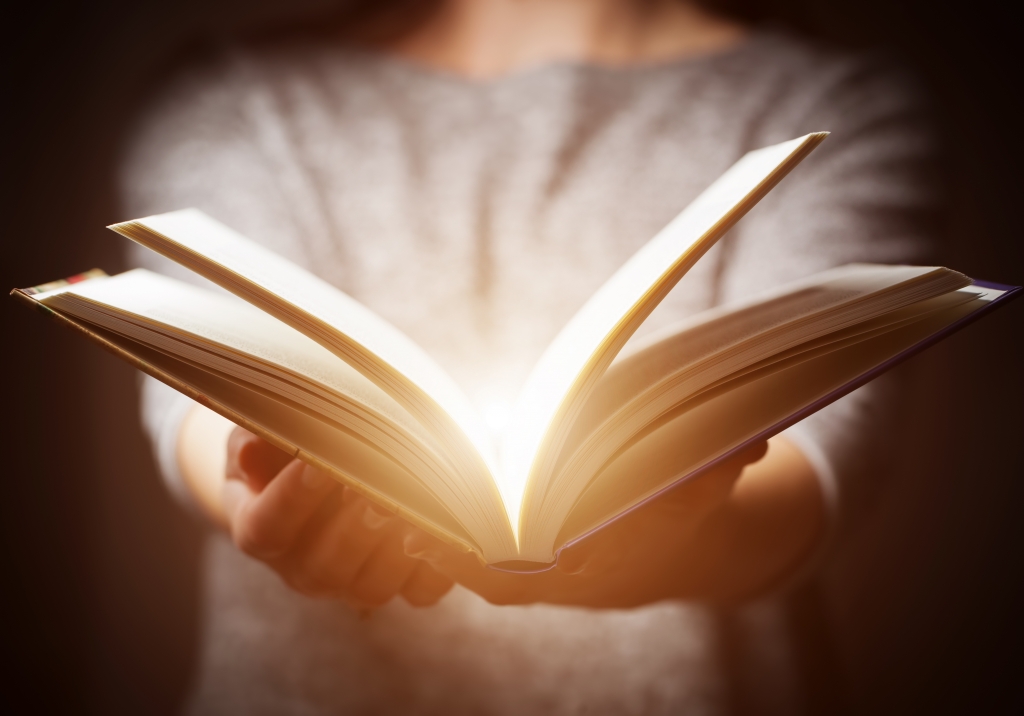
書籍『空室対策100選』発売中!
オーナーズエージェントでは、空室対策アイデアを100個つめ込んだハンドブック『空室対策100選』を好評発売中です。
営業社員に1冊持たせておくだけで、空室対策提案の採用率がぐんと高まります。オーナー提案ツールとして、この機会にぜひお役立てください。
●「バイク置き場新設」の掲載ページ(サンプル)











 相談してみる
相談してみる
