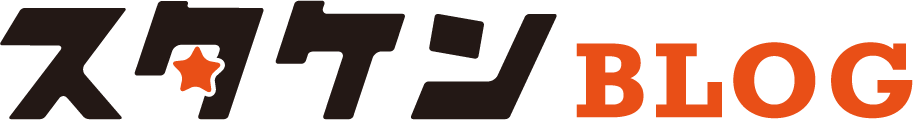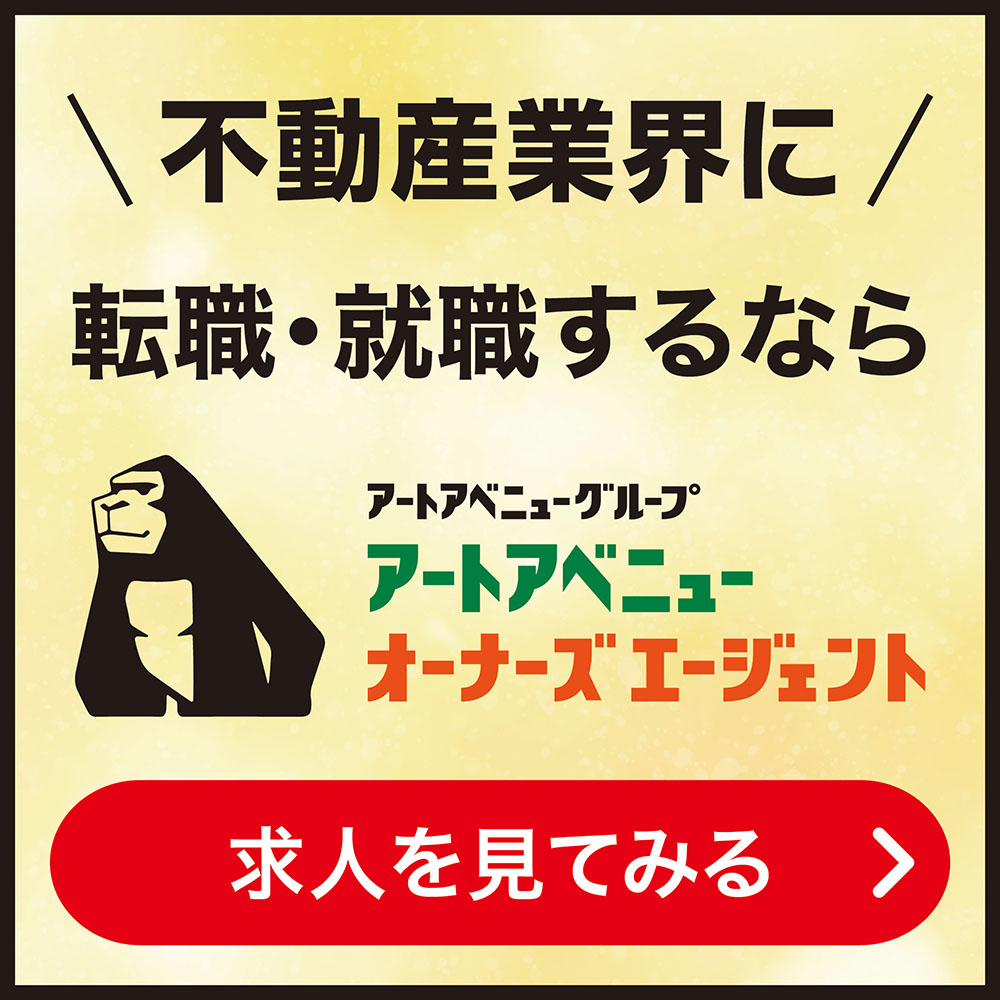「宅建の過去問はどうやって活用すればいいの?」
「宅建に過去問学習が必要な理由は?」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
宅建は、過去問を活用して学習すると、最も合格に近づけます。
テキストで学習した内容が記憶に定着しない方は、過去問をアウトプットのツールとして活用する方法がおすすめです。
そこで、今回は宅建に過去問学習が必要な理由や勉強方法について詳しく解説していきます。
過去問が必要な理由や活用方法がわからない方は、ぜひ参考にしてください。
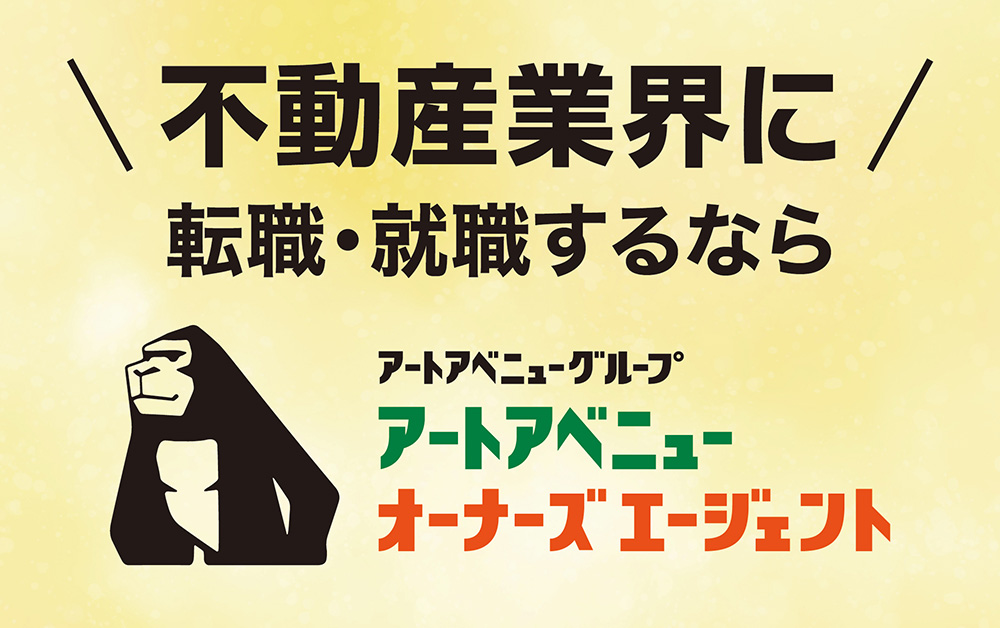
\ 積極採用中!/
この記事で学べること
宅建に過去問学習が必要な理由

宅建に過去問学習が必要な理由は、以下3つです。
- 過去問から出される問題が多いため
- 試験と同じ形式になれるため
- 知識を定着させるため
過去問学習を始めようと検討している方は、ぜひ参考にしてください。
過去問から出される問題が多いため
宅建試験は、毎年過去問の類題から7割程度出題されています。
過去問からの出題が多いため、内容がわかると本試験でも解けるようになり、得点につながりやすくなります。
仮に、過去問を使わずテキストのみで勉強した場合、問題の傾向が掴めず勉強時間を無駄にする可能性が高いです。
効率良く宅建合格を目指したい方は、テキストのみに絞るのではなく、過去問を活用した学習に切り替えましょう。
試験と同じ形式に慣れるため
過去問は、過去に行われた本試験の問題が掲載されているため、本番と同じ形式で学習を進めることも可能です。
本番前に時間配分や傾向を掴んでおくと、本試験でも焦らず実力を最大限発揮できます。
問題の傾向を掴み、1問にかけられる時間を把握してから本試験に臨みましょう。
また、問題構成が変化すると、類題が出題されても正解が分からなくなってしまうことも少なくありません。
過去問を繰り返し解くと、さまざまなパターンの問題形式に慣れてくるため、類題でも正解できる実力が身につきます。
知識を定着させるため
過去問を解くと、知識を定着させることができます。過去問学習は、テキストで覚えた内容をアウトプットする作業です。
テキストを読んだ後にいざ問題を解いてみると、覚えたはずの内容を思い出せず、間違えてしまうケースも少なくありません。
人間の脳は、1日後には約70%のことを忘れてしまうため、テキストの内容を覚えて理解してもアウトプットの作業で問題を間違えてしまいます。
アウトプットの作業で問題を間違えないためには、過去問を間違えながらも繰り返し解く必要があります。
間違えた体験は、人間の脳に鮮明に記憶されるため、知識を深く定着させることが可能です。
本試験で間違えてしまったら不合格ですが、過去問では何度間違えても試験に影響しないため、失敗を恐れず過去問にチャレンジしましょう。
また、宅建試験ではひっかけ問題も出題されます。
出題されるひっかけのパターンに慣れるためには、繰り返し解きながら知識を定着させる方法が効果的です。
過去問学習で知識を定着させ、本番試験で回答できる「ノウハウ」をマスターしましょう。
宅建は過去問だけで合格できる?

宅建試験は、過去問だけ学習しても「合格はほぼ不可能」です。
過去問学習では、「過去宅建試験に出された問題を解き、採点して解説を読む」という作業を繰り返し行います。
そのため、知識がなければ問題を解くことはできず、過去問で基礎知識を習得できるのは解説部分のみとなってしまいます。
解説をすべて読んで覚えていくのでは膨大な時間を要するため、宅建試験に求められる知識を網羅するのは現実的に考えて難しいです。
また、宅建試験は近年難化傾向にあり、もはや過去問だけで合格できる試験ではなくなっています。
テキストを利用した独学か通信講座を利用し、専門的な知識をインプットしなければ合格は厳しいでしょう。
宅建過去問の種類
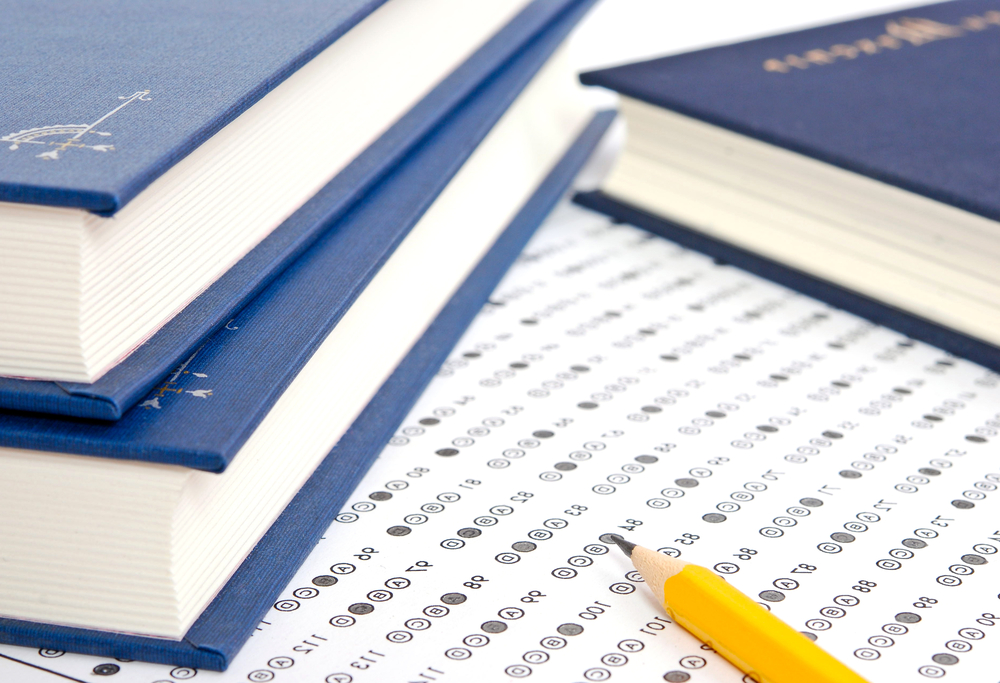
宅建過去問は、大きく分けて「年度別問題集」と「科目別&出る順問題集」の2種類が存在します。
この項目では、それぞれの特徴や使い方を詳しく解説します。
年度別問題集
年度別問題集は「令和4年度分」「令和3年度分」「令和2年度分」など、実際に行われた試験問題をそのまま掲載している問題集です。
以下の項目に当てはまる方は、年度別問題集がおすすめです。
- 時間配分が苦手な方
- 本番形式で過去問を解きたい方
- テキストで基礎知識を習得した方
試験本番は、2時間という限られた時間で50問を解きます。
2時間と聞くと長く感じる方も多いですが、実際に問題を解いてみると、制限時間ギリギリまで時間を必要とします。
そこで、年度別問題集を活用して本番形式で学習すると、本試験で上手く時間配分できるはずです。
年度別問題集を活用し、本試験でも焦らず問題を解ける能力を身につけましょう。
科目別&出る順問題集
科目別&出る順問題集は、科目別・項目別に過去問から抜粋されている問題集です。
科目別・項目別に類似問題がまとまっているため、学んだ項目の出題パターンを深く知ることができます。
また、項目別に並んだ問題は、過去問に頻出される順番になっているテキストが多い点も魅力の1つです。
過去問をひたすら解くだけでは、問題の傾向を掴めず、効率の悪い勉強方法になってしまいます。
しかし、「出る順問題集」ではテキストを解くだけで問題の傾向を掴めるため、要点を効率良く抑えられるでしょう。
以下の項目に当てはまる方は、科目別&出る順問題集がおすすめです。
- 苦手な項目を繰り返し解きたい方
- 宅建の問題を解いた経験がない方
- 出題される問題傾向を分析することが苦手な方
年度別問題集の内容が難しいと感じている方は、「科目別&出る順問題集」を解いてテキストの内容をアウトプットする方法がおすすめです。
「年度別問題集」は実際の試験を知るため、「科目別&出る順問題集」は知識を定着させるため、同じ過去問集でも目的が違います。
2種類のテキストを用途によって使い分け、最短で宅建合格を目指せるようにしましょう。
宅建過去問の勉強法とは?

宅建は、過去問をひたすら解くだけで合格できるほど甘い資格ではありません。
この項目では、宅建過去問の勉強法を以下3つご紹介します。
- 過去問は過去10年分解く
- 最低3周する
- 間違えた問題は解説できるようになるまで繰り返す
過去問の活用方法に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
過去問は過去10年分解く
おすすめの勉強方法は、過去10年分解くことです。
宅建の過去問は、テキストによって掲載されている年数が異なりますが、おすすめは過去10年分掲載されている教材です。
3~5年分掲載されている過去問題集の場合、解ける問題数は150~250問と、ボリュームが少なめです。
一方、10年分の過去問題集の場合は、500問以上の問題を知ることができます。
過去問から出される問題が7割以上と言われている宅建試験なので、より多くの問題を知っておいた方が類題に対応でき、本番試験で有利になります。
また、数年ごとに出題される問題もあるため、3年よりも前に出題された問題が本試験の問題になる可能性も高いです。
たくさんの問題を把握してもマイナスにはならないので、過去10年分は経験しておくと良いでしょう。
最低3周する
過去問学習の際は、決めた年数分を最低3周しましょう。
3周しなければ内容を覚えることができず、過去問学習の意味がなくなってしまいます。
1周ごとに以下のようなことを意識して勉強を進めると効果的です。
| 1周目 | まずは1年分ずつ本番と同様に問題を解いていきましょう。採点後、問題ごとに「正解した問題」「間違えた問題」「正解したけどその理由が分からなかった問題」の区別をつけ、後者2つについては解説を読んで理解するようにしてください。 |
| 2周目 | 1周目と同じ内容を繰り返します。この時点で、「正解して解説までできた問題」については復習する必要はありません。 |
| 3周目 | 本番どおり問題を解き、解説までできない問題を徹底的に勉強していきます。 |
間違えた問題は解説できるようになるまで繰り返す
1度でも間違えた問題は、正解するだけでなく解説できるようになるまで繰り返し解きましょう。
個人差はありますが、同じ問題を2周3周すると問題や解答を覚えてしまいます。
問題を覚えてしまうと、前回間違えた問題を克服し、「解けるようになった」と勘違いしてしまうことがよくあるのです。
宅建あるあるですが、これは内容を理解できているわけではなく、問題を覚えてしまっているだけです。
問題の形式が変わったときに対応できなくなってしまうため、正解が分かっている場合でも理由を考えながら解き、採点時に正しく理解しているか確認する必要があります。
また、同じ問題を何度も間違えてしまう場合は、苦手に感じている分野の可能性があります。
苦手に感じている分野は、テキストから読み直し、理解して解くことを繰り返し行うと良いでしょう。
宅建過去問学習の注意点

宅建を過去問学習する際は、注意するべきポイントが以下3つあります。
- 最新版を購入して使う
- 自分が読みやすい本を選ぶ
- 解説も必ず読んで理解する
注意点を理解し、正しい学習方法で宅建合格を目指しましょう。
最新版を購入して使う
宅建の過去問集は、法改正によって解説の内容が変化するため、最新版を購入する必要があります。
昔の過去問集を利用する場合、類題でも「この年は1が正解だったけど、法改正後の今は3が正解になる」といった、解釈の不一致が発生してしまいます。
一方、最新版の過去問集を利用する場合は、古い年度の問題でも解説されているため対応可能です。
たった1年古いという場合でも使用は避け、最新版を購入しましょう。
自分が読みやすい本を選ぶ
宅建の過去問集を選ぶ際は、自分が読みやすいと感じるものを選びましょう。
過去問集にもさまざまな種類があり、出版社によって文字の大きさや解説の文字量、レイアウトが異なります。
また、解説の位置がテキストによって変化するため、自分が勉強しやすい流れになっているかも重要です。
以下の表では、解説の位置によって変化するメリット・デメリットをまとめているので、ぜひ参考にしてください。
| 解説の位置 | メリット | デメリット |
| 解説が後ろについているテキスト | 問題を解いてもすぐに解説を確認できないため、出題内容に集中できる。 | 解いた後すぐに解説を確認しづらいため、問題を解いた時にどのような考え方をしたのか分かりづらい。 |
| 解説が1問ごとに設置されているテキスト | 解いた後すぐに解説を確認できるため、リアルタイムで自分の間違えた場所を把握できる。 | 解説を見るのが習慣化してしまい、本番で正解できる能力が身につきづらい。 |
「過去問の種類が多くて選べない!」という方は、購入したテキストと同じ出版社の過去問集がおすすめです。
同じ出版社の過去問は、テキストと連動して解説されているケースが多いため、インプットとアウトプットを同時に行うことができるでしょう。
解説も必ず読んで理解する
宅建の過去問を活用して学習する際は、必ず解説まで読んで理解しましょう。
問題を解いて正誤を知るだけでは対策にもならず、同じ問題が出ても間違えてしまいます。
「なぜ間違えたのか」「なぜ正解したのか」をきちんと自分で説明できなければ理解できているとは言えません。
解説を見ると答えの理由が記載されているため、本番試験で類題が出題されても「正しく回答できる能力」が身につきます。
解説の内容が難しいと感じた場合は、テキストで同じ分野を見返すと言葉が砕けて理解しやすくなるでしょう。
過去問学習とあわせてやるべきこと

過去問で試験勉強を進めたからといって、必ず合格できるわけではありません。
どのような問題でも素早く回答できるように瞬発力や応用力を習得することも必要です。
この項目では、本試験で実力を発揮するために必要な取り組みを2つご紹介します。
模試を受ける
宅建試験の直前対策としてよく挙げられますが、模試を受けることは非常に重要な試験対策となります。
模試は本番試験のシミュレーションができることに加え、今の自分の実力を試すこともできるため、宅建に合格できる可能性が高まります。
ただし、模試を受ける回数は多くても3〜4回に留めるようにしましょう。
模試は、本番形式に限りなく近い力試しなので、回数をこなしても自分の実力が高まるわけではありません。
ある程度過去問を解けるようになってから模試を受け、本番合格に近づけているか判断するツールとして利用する必要があります。
スマホアプリの活用
スキマ時間を使って勉強できるスマホアプリを活用しましょう。
スマホアプリでは過去問や模試の問題を解けるだけでなく、一問一答形式や四択形式の問題を解くことができます。
そのためより多くの問題を解くことができ、正しい答えを即時に導くための瞬発力が身に付きます。
学習時間・学習日数・朝鮮問題数・正答率・連続正答数・1日の平均勉強時間をアプリが記録しているため、自身の傾向や苦手な分野を一目で把握できるでしょう。
受験者同士が気軽に情報交換できる「掲示板機能」も備わっているため、モチベーションの維持も簡単に行えるはずです。
まとめ

今回は、宅建学習に過去問が必要な理由や勉強方法について詳しく解説しました。
宅建の過去問を利用すると、本番形式で学習を進められるだけでなく、テキストでインプットした内容をアウトプットするツールとしても活用できます。
テキストでインプットした内容を記憶に定着できていない方は、上記でご紹介した宅建過去問の活用方法を参考に、学習方法を変えてみましょう。
また、過去問とテキストを利用した独学に苦戦している方は「通信講座」の受講がおすすめです。
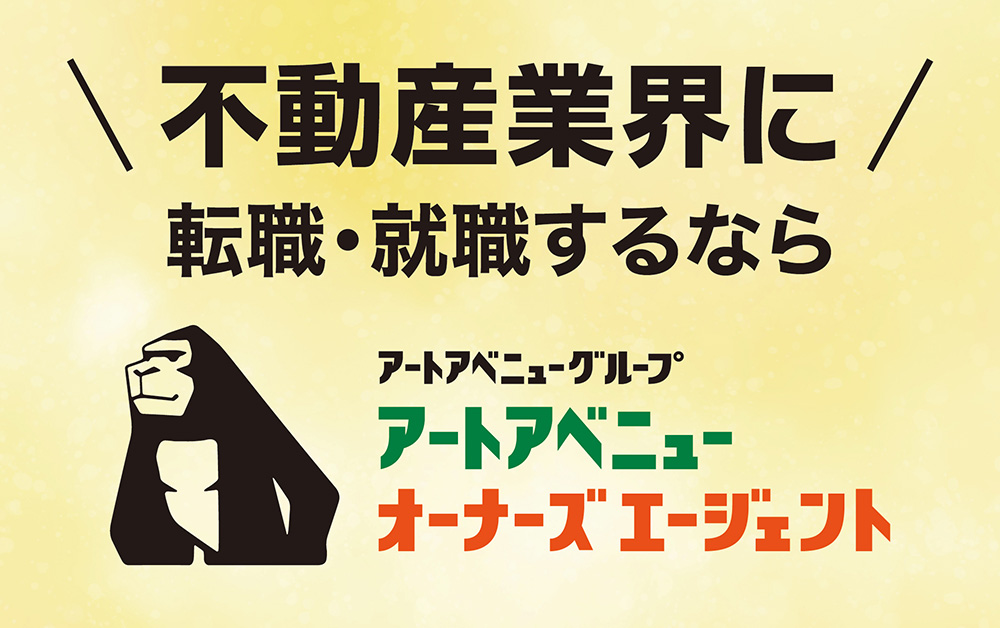
\ 積極採用中!/
最新記事 by ガースー (全て見る)
- 宅建を復習する効率的な学習テクニック - 2024年3月25日
- 宅建の難易度は?過去10年間の推移を解説 - 2024年3月25日
- 宅建合格に必要な勉強時間が200時間〜300時間って本当? - 2024年3月25日
- 2024年(令和6年度)宅建試験日&宅建申込スケジュールが決定! - 2024年3月21日