「オフィスを飛び出しやってみた。」
このコーナーは、読者の皆さまに賃貸管理の「今」をお伝えするべく、弊社社員がオフィスを飛び出し、社内外のさまざまなイベントに参加する企画です。
この記事では、業界で横のつながりを持ちたい方、研修・交流会に興味がある方に向けて、日本賃貸住宅管理協会(日管協)東京都支部が主催する「歴史系イベント」をレポート形式でお伝えします。
小田原の「歴史」を味わう風変わりな研修ツアー

研修ツアーには会員ら12名が参加
去る2020年11月21日——、
日管協・東京都支部が主催するイベント「研修ツアー 第4回歴史ウォーキング 戦国時代最大の城郭・小田原城総構えを歩く」に参加してきました。
きっかけは、ある日、ふと目に留まった日管協のメールマガジン。
そこに書かれていた、賃貸管理の「研修ツアー」と「歴史ウォーキング」のふしぎな取り合わせに、「え、どういうこと?」と思わず興味をそそられたのです。
実はこのイベント、日管協の東京都支部が年1回のペースで開催している人気企画で、同支部の事務局長・関一則さんをガイド役に、日本各地の史跡を見て回り、合わせて賃貸住宅についても見聞を広めようとするもの。
開催の目的は、やはり研修ですので「賃貸住宅の知識拡充」が第一。
さらに、史跡散策をとおして「会員間の親睦を深めること」、さまざまな人と接して「コミュニケーションスキルを磨くこと」、長距離を歩いて「健康増進を図ること」といった目的も掲げており、なかなかに欲張りなイベントとなっています。
特に歩くことには妥協がないようで、毎回参加している会員さん曰く「10kmオーバーは当たり前」なんだとか。加えて、山などの足を滑らせる場所でなければ雨天強行。
体力づくりだけでなく、「最近太ってきたな」という方にも打ってつけのイベントと言えるでしょう。
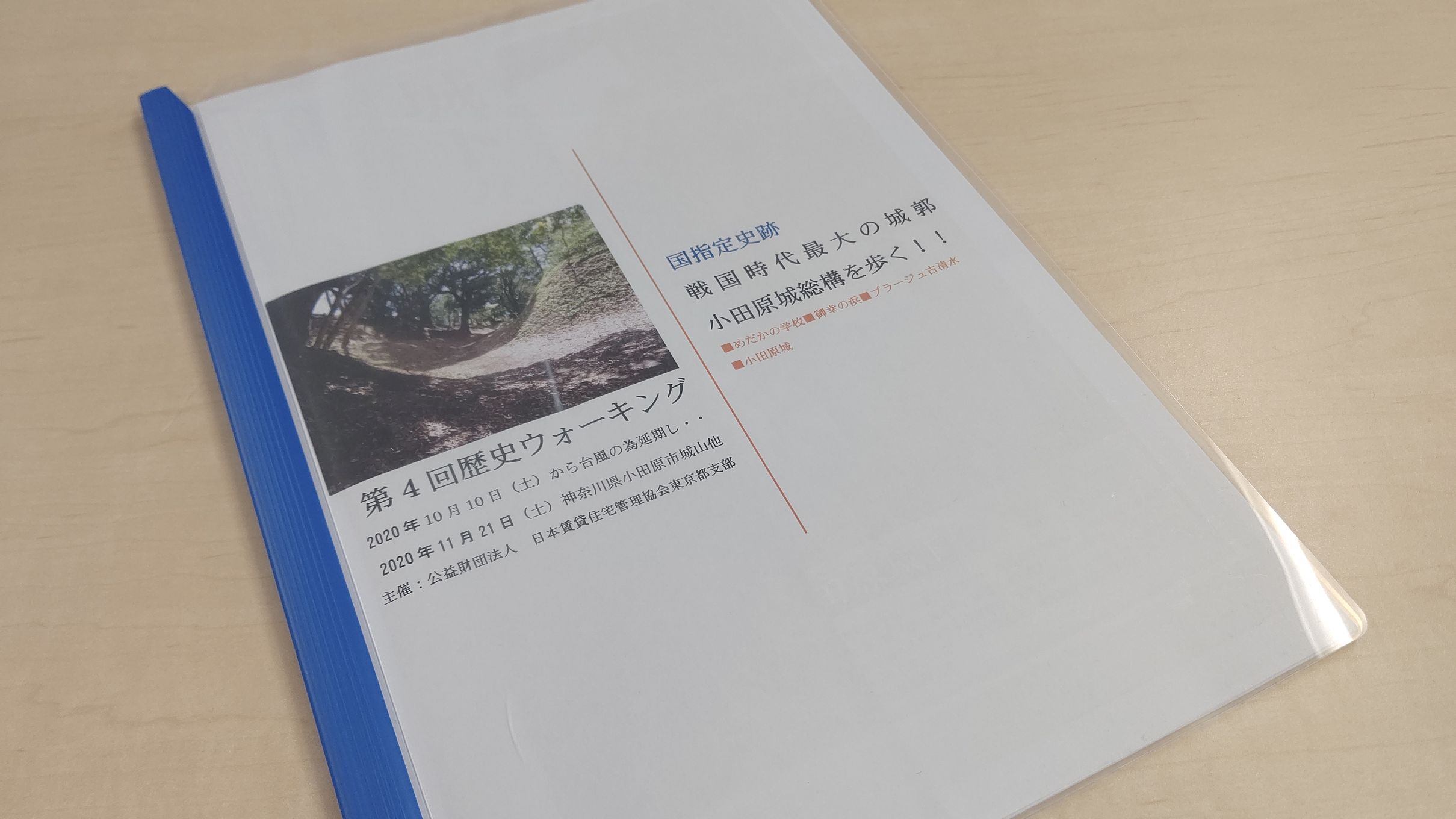
ガイド役の関さん手作りのツアー資料。読み応え抜群!
さて、4回目となる今回のテーマは「戦国時代最大の城郭・小田原城総構え(※)を歩く」。
訪れたのは小田原市の観光名所「小田原城」とその周辺でした。
(※総構え〈そうがまえ〉:城下町全体を要塞化するために町の外周を取り囲んだ土塁や堀のこと)
研修内容は盛りだくさんで、小田原の町全体を取り囲んだ戦国時代の土塁と堀を見て回り、海辺に出て相模湾を眺めた後、小田原ゆかりの地主オーナーが営む賃貸住宅を見学しようというものです。
ガイド役の関さんの「これから戦国時代にタイムスリップします!」という声を狼煙に、日ごろ賃貸管理に勤しむ会員の皆さんと小田原駅を出発。その昔、武田信玄や上杉謙信を撃退したという総構えの、今なお残る防御陣地をめぐりました。
まずは史跡散策。小田原城総構えを歩く

遺構を目指して歩き続ける
今回の歴史ウォーキングでは、400年前の小田原城を散策。
今ではすっかり住宅地ですが、かつての城内と城外を分ける境界線をなぞるように進みました。城内に侵入しようとする敵をくい止めるのが城ですから、城内外の境を歩けば、自然と防御陣地の遺構に行き当たるというというわけです。

深さ10mの空堀が広がる「稲荷森」
写真の場所は、孟宗竹が群生する「稲荷森」という名前の遺構です。断崖のような深い空堀が広がり、下から攻め上る敵を寄せ付けない造りになっています。

幅20~30m、深さ11mの「小峯御鐘ノ台大堀切東堀」
数ある防御陣地の中で、とりわけ参加者を唸らせた巨大空堀。小田原城を攻める敵は、城兵の攻撃に耐えながら、この空堀を渡らなければなりません。

明治天皇・皇后が訪れた「御幸の浜」
小田原城の総構えを抜けると、かつて明治天皇・皇后が訪れたという「御幸の浜」と相模湾が広がっていました。戦国末期に起きた豊臣秀吉の小田原征伐では、この海に秀吉軍の軍船がひしめいたそうです。

堀の傾斜に見事な巨木。戦国時代にもあったかもしれないと思うと感慨深い

小田原城天守閣の前で記念写真

ツアーの終わりに北条氏の墓に手を合わせた。二つの墓石は北条氏政・氏照兄弟のもの
充実した歴史ウォーキングもあっという間に3時間。
総距離にして約13kmを歩いたところで、いよいよ本題へ。
しばしの休憩を挟んだ後、研修ツアーの一行が向かったのは研修先のとある物件。そこは戦国時代から今日まで、小田原に代々暮らしてきた地主オーナーの、地元愛にあふれる賃貸住宅でした。
地域に根差した賃貸管理「プラージュ古清水」

プラージュ古清水の外観
訪れたのは、小田原駅から徒歩13分の距離にある賃貸住宅「プラージュ古清水」。
RC造9階建てで、戸数は全68戸。高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)として2010年3月に竣工し、1階にはデイサービスの事業所が入っています。快適な住み心地や、相模湾を見渡す素晴らしい眺望、恵まれた周辺環境から入居者が後を絶たない人気物件です。
間取りは1Kと2Kの2種類で、現在の家賃帯は1K(約28㎡)5.7~7.5万円、2K(約48㎡)9.9~11.9万円。一方、高齢者向けは月額支払い型プランで8.2~14.4万円とのこと(2020年12月21日現在)。
しかし、普通の賃貸住宅ではなく、どうして高円賃からのスタートだったのでしょうか。案内をしてくれたオーナーの清水修一郎さんにお話をうかがいました。

ツアーを案内する清水さん
清水さん「賃貸住宅を始めるとき、少しでも地元の役に立てないかと考えたのがきっかけでした。知り合いに相談したところ、高齢者の住む場所が足りていないことを知りまして、それならと高齢者用住宅を建てることに決めたんです。
高円賃の制度が廃止になったことで若い人も入居できる複合マンションに切り替えましたが、今でも多くの高齢者にご利用いただいています。ちなみに、若い女性入居者もかなり多いんですよ。高齢者用にセキュリティを高くしたことが人気みたいです」
プラージュ古清水の一番の特徴は、入居者とお客さんが歓談できるキッチン付きの談話室が各階にあること。10畳ほどの空間に机と椅子が置いてあり、端にはカウンターキッチンを配置。ベランダからは海が一望できます。

ゆっくりお喋りを楽しめる談話室
清水さん「外からお客さんが訪れたときに、入居者さんがお喋りをゆっくり楽しめる空間があればいいなと思い、賃貸用の空間を削って談話室を設置しました。お部屋に招くとなると片付けもしなくちゃならないですし、お客さんも気を遣ってしまいますからね。談話室は1階を除く全フロアーの角部屋にありますので眺めも良いんです。会話も弾みますよ」
続けて清水さんは、「(賃貸住宅で)こういう無駄な空間を作ろうとするのは旅館のサービス業の視点」と話します。実は清水さん、プラージュ古清水を建てる前は、同じ場所で「古清水旅館」という老舗旅館を営んでいました。
清水さん「江戸時代、ここは大名や公家などが泊まる貴人用の宿所だったんです。明治になってからは大衆旅館を始め、平成の初めごろまで営業しました。
そうした経緯から、当家には歴史的価値の高い品々が多く残されていますので、プラージュ古清水の2階には歴史資料室を設けて資料を展示しています。資料室は家賃こそ生みませんが、小田原の歴史を知ることのできる大切な場所。今後も残していきたいですね」
プラージュ古清水では、夏に屋上で入居者や地域住民らと花火を見物するなど、地域交流のイベントも開催してきたそうです。お部屋を借りづらい高齢者の住まいとして、地域の語らいの場として、地元小田原に根差した心温まる賃貸住宅の形がここにはありました。
そして、清水さんに歴史と物件の両方の話をたっぷり聞かせていただき、はじめ疑問に感じた「研修ツアー」と「歴史ウォーキング」の取り合わせにもようやく納得できたところで、研修ツアーは無事終了。
その後、毎回恒例となっている楽しい酒盛りの時間を迎えました(皆さん、ウキウキでした…笑)。

高齢者のため廊下には手すりを付けている

各階のエレベーター前にはオートロックが完備。セキュリティは抜群だ

新聞用ポストが各階に設置。1階集合ポストと使い分け、入居者の手間を減らしている

屋上から見下ろす町並み。中央に旧東海道が走る

目線を変えれば相模湾を一望できるロケーション
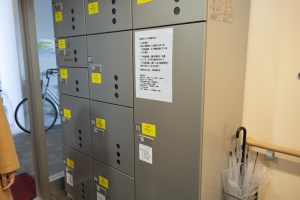
大型の宅配ボックスで利便性UP
歴史ウォーキング、2021年から「年2回」開催か!
賃貸住宅について実地に学びながら、会員間で親睦を深め合える歴史ウォーキング。
日ごろ忙しい管理会社の方にとって、横のつながりを持てる良い機会になるはずです。
また、史跡散策と聞いて「あまり歴史は知らないんだよな」という方でも全く心配いりません。歴史好きの方々が嬉々として教えてくれますし、意外と歴史以外の話に花が咲いたりするものです。
事務局によりますと、2021年からは年2回の開催を予定しているとのこと。
少しでも興味のある方は、ぜひ一度参加してみてください!
【後書き】小田原の歴史話。小田原城と小田原宿について

資料室で小田原の歴史話に耳を傾けた
余談になりますが、戦国時代、関東では小田原城を本拠地に戦国大名・北条氏が大勢力を築いていました。しかし、その支配は盤石ではなかったようで、急速に拡大したことから周辺の敵対勢力に包囲網を敷かれ、さらには越後の上杉謙信、甲斐の武田信玄なども敵に回してしまいます。
そのため、北条氏は何度か滅亡の危機を迎えるのですが、そのたびに窮地を救ってくれたのが難攻不落の小田原城であり、町全体を土塁と堀で囲った大規模外郭・総構えでした。
小田原城の攻めにくさは相当だったようで、天下人となった豊臣秀吉が約16万の大軍をあげて城を包囲した時も、力攻めによる落城はついにできず。持久戦となり、最後は根負けした北条氏の降伏・開城となりました。
宿場として栄えた小田原
平和な江戸時代になると、大要塞としての小田原は影をひそめ、東海道で最大規模を誇る小田原宿(おだわら・しゅく)として発展を遂げることになります。
旅籠の数は100軒を超え、参勤交代の大名や朝廷の使者といった貴人が休泊する本陣・脇本陣も複数あったとのこと。
その本陣・脇本陣の一つを経営した名家が、今回の歴史ウォーキングで物件の案内をしてくれた清水修一郎さんの清水家でした。
清水さん「参勤交代で江戸を行き来する多くの大名をお世話した本陣ですが、お役目こそ名誉であるものの、大変な負担だったそうです。大名を宿場全体でお迎えしなければなりませんから、大名が来ると分かると町中にお触れを出し、皆で道を掃き清め、地元の産物を献上するなど接待に努めたと言います。
でも、相手は一国の主。相応のお代をいただけるんじゃないかと思うじゃないですか。とんでもないんです。散々おもてなしをしても、宿泊料は寸志程度。形式的に支払われるだけでしたので全くの赤字だったとか…。清水家に限らず、どこの本陣も資金繰りに困っていたそうですよ」
とはいえ、本陣・脇本陣を任されたのは地域の有力者だからこそ。
清水さんが脇本陣跡地で賃貸住宅を営んでいるように、地主オーナーとして賃貸経営をされている方のなかには、かつて宿場で本陣・脇本陣を経営していたという名家の歴史が隠れている可能性も。オーナーさんとの話の種に、家の歴史を尋ねてみるのも面白いかもしれませんね。










 相談してみる
相談してみる
