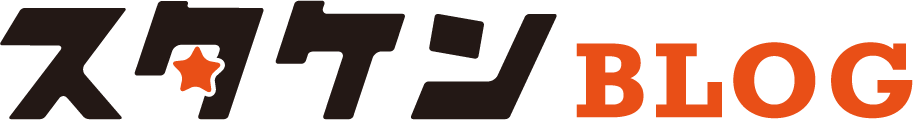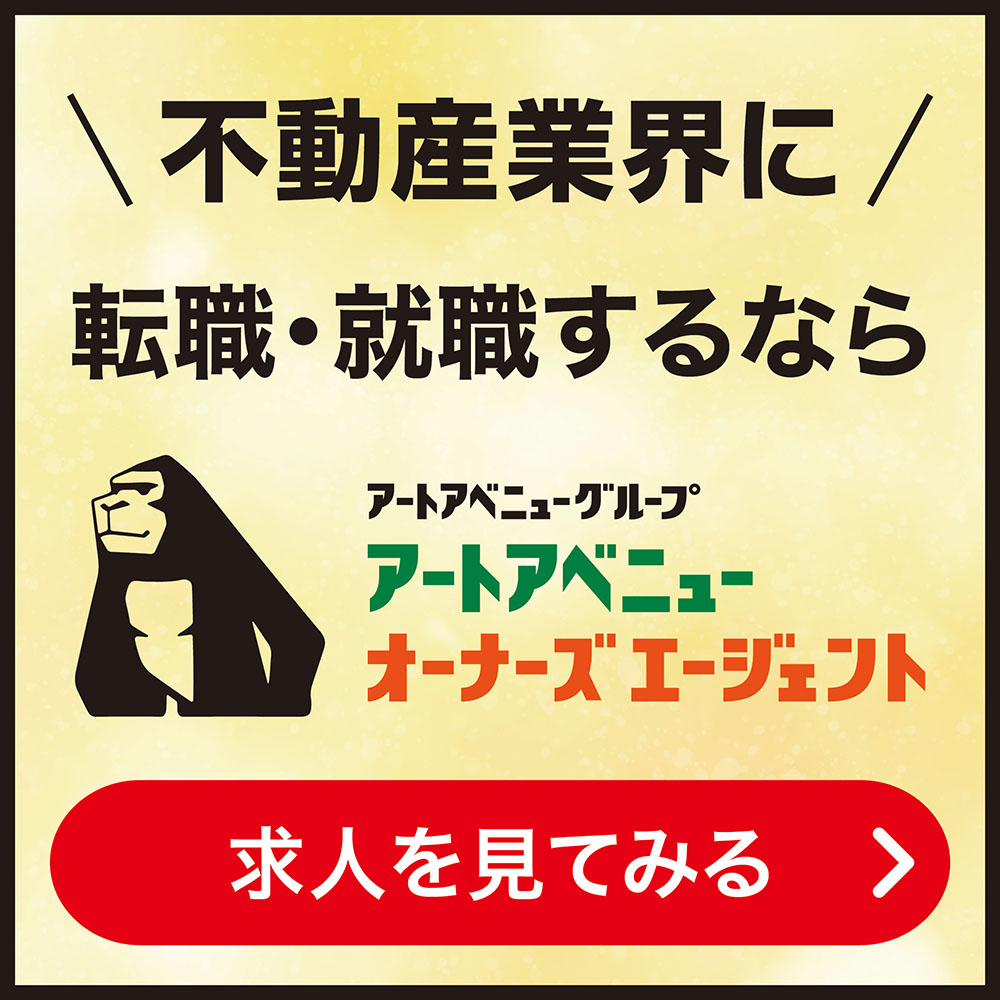「宅建業法の試験攻略方法は?」
「宅建業法は2023年どこが改正されたの?」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
宅建学習の4つの分野の中で、特に合格の鍵を握っているのは、宅建業法です。
宅建業法は、宅建本試験50問のうち20問出題されるため、満点を目指して勉強する必要があります。
そこで、今回は宅建業法の得点を上げる方法や2023年の法改正について詳しく解説します。
本記事を最後まで読むと、宅建業法の攻略ポイントや改正点がわかり、宅建の合格に近づくはずです。
宅建の合格を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
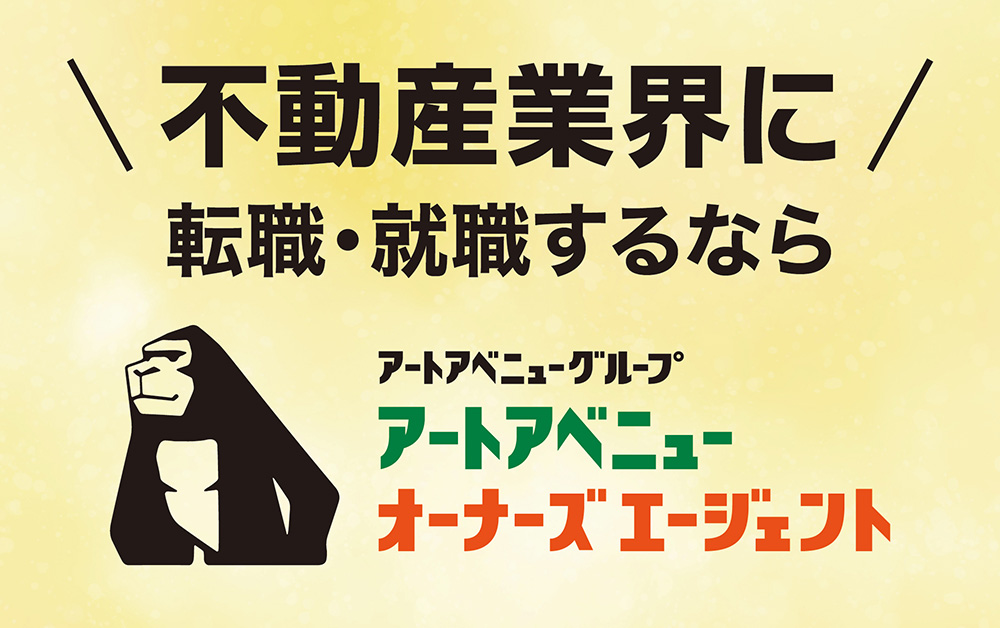
\ 積極採用中!/
この記事で学べること
宅建業法とは

宅建業法は、宅建業者が業務の適正な運営を行い、一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
つまり、宅建業者が一般の方をだまして不正な取引をしないようルールを定めているのです。
宅建業法の内容は宅建士の仕事に直結しており、試験では50問中20問が出題されるメイン分野となっています。
宅建業法に限る合格者の正解率は9割を超えているため、合格者は必ず得点している分野といえます。
学習内容は、主に以下の通りです。
- 宅建業とは
- 不動産屋が宅建業の免許を取得するために行わなければならないこと
- 宅建業免許取得後にやらなければならないこと、やってはいけないこと
- 宅建士資格の登録方法や業務内容
- 宅建業者の業務内容、契約時の重要事項
- 仲介手数料の計算方法
学習内容を見ると、専門的な単語が多く、難しく感じる方も多いはずです。
しかし、宅建業を営む上での基本的な内容になるため、テキストを読み込んで過去問学習を行うと知識が定着しやすいです。
宅建業法について深く理解し、本試験で満点を狙えるように学習を進めていきましょう。
宅建業法の勉強を始める前に身につけるべき基礎知識

この項目では、宅建業法の勉強を始める前に身につけるべき基礎知識について詳しく解説します。
初学者の方は、以下4つの知識を頭に入れた上で学習を進めていきましょう。
- 宅建業について
- 宅建業を営むには免許が必要
- 宅建業の免許が不要な段位
- 免許の種類や申請場所
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
宅建業について
宅建業とは、「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うことです。
宅建業における「宅地」とは
- 用途地域内にある土地
- 現在建物が建っている土地
- 建物を建てる目的で取引される土地
の3種類を指し、いずれも登記簿上の地目は関係ありません。
例えば、登記簿に「畑」と書かれていたとしても、その土地が家を建てる目的で取引をされている場合は「宅地」に該当します。
ただし、用途地域内にある土地であったとしても、広場・公園・道路・水路・河川である場合は対象から除外されます。
宅建業における「建物」とは
建物の定義は、土地に定着した建造物であり、建物として使用可能なものを指します。
倉庫やマンションの一室も建物として扱う点は、注意が必要です。
宅建業における「取引」とは
宅建業における取引は、以下8つが該当します。
- 自ら「売買」「交換」
- 他社の代理で「売買」「交換」「賃借」
- 他社の媒介で「売買」「交換」「賃借」
自らの賃借は取引に当てはまらず、転貸も取引に当たらない点は、注意が必要です。
宅建業における「業」とは
宅建業における「業」とは、不特定多数の人に反復継続して取引することです。
自社の従業員に限定して建物を売買する場合や、一括して売却した場合には業に当たりません。
ただし、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割して行う宅地の販売等複数の物に対して行われるものは、反復継続的な取引に該当する点は注意が必要です。
宅建業を営むには免許が必要
宅建業を営むには、免許が必要です。
免許の有効期間は5年間となっており、5年経過ごとに更新しなければいけません。
また、免許の更新は、有効期間満了日の90日前から30前までに手続きを行う必要があります。
なお、免許を更新したのにも関わらず新しい免許証が手元に届かない場合、更新前の免許が有効なものとして扱われます。
宅建業の免許が不要な団体
宅建業を行うには、原則免許が必要ですが、以下2つの団体は免許が不要です。
- 国・地方公共団体
- 信託会社・信託銀行
国・地方公共団体
国や地方公共団体が宅建業を行う場合、免許は不要です。
また、宅建業のルールも適用対象外となります。
信託会社・信託銀行
信託会社や信託銀行が宅建業を行う場合も、免許は不要です。
ただし、国・地方公共団体と違い、宅建業のルールは適用される点は注意が必要です。
また、一定事項を国土交通大臣に届ける義務も設けられています。
免許の種類や申請場所
宅建業の免許の種類
宅建業を営むための免許は、以下2種類存在します。
- 都道府県知事免許:1つの都道府県内に事務所がある
- 国土交通大臣免許:複数の都道府県内に事務所がある
事務所の数や規模ではなく、あくまで所在地で決まると覚えておきましょう。
例えば、東京と大阪に1つずつ事務所を構えている場合、国土交通大臣免許を発行します。
一方、東京都内に事務所が30ヶ所ある場合は、全て同一の都道府県内なので都道府県知事免許をもらいます。
免許の申請場所
免許を申請する場合、免許申請書を免許権者に提出しなければいけません。
免許権者とは、都道府県知事や国土交通大臣などの、免許を与えた人のことです。
申請する免許権者によって、以下の通り提出方法が異なります。
- 都道府県知事免許:知事に直接申請する
- 国土交通大臣免許:主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して申請する
宅建業法の2023年改正ポイント

本試験に関係する宅建業法の2023年改正ポイントは、主に以下2つです。
- 不動産取引の電子化
- 住宅瑕疵担保履行法
それぞれ詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
不動産取引の電子化
宅建業法は、「デジタル社会」の形成を目的としたデジタル改革関連法整備の一環として、法改正が行われました。
変更箇所は、以下の通りです。
宅建業法上必要とされていた、下記の押印が不要となりました
- 重要事項説明書(35条書面)への宅建士の押印
- 宅地建物の売買・交換・賃貸契約締結後の交付書面(37条書面)への宅建士の押印
以下の書面交付につき、電磁的記録による交付が可能となりました
- 重要事項説明書(35条書面)
- 売買・交換・賃貸契約締結時の交付書面(37条書面)
- 媒介契約締結時の交付書面
- レインズ登録時の交付書面
宅建士の記名押印が必要だった35条書面・37条書面に押印が不要となりました。
ただし、媒介契約書面は変わらず宅建業者の記名+押印が必要になるため、注意しましょう。
また、35条書面・37条書面・媒介(代理)契約書面・レインズ登録時の交付書面は、交付相手(取引の相手方や依頼書など)の承諾を得て電子交付も可能です。
ただし、従来通りクーリング・オフの通知には書面が必要という点は、注意が必要です。
住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保履行法も、電子化が行われています。
自ら売主となり新築住宅を販売した宅建業者は「供託」または「保険」の資力確保処置を講ずる義務がありますが、それぞれに必要な「供託所の所在地等を記載した書面」「保険証券またはこれに代わる書面」について、電子交付が可能になりました。
ただし、供託所の説明書面を電子交付する場合は、買主や発注者の承諾が必要となる点は注意が必要です。
宅建業法の出題傾向

宅建業法は出題数20問と、全体の4割を占めています。
覚える量も他の分野に比べてそれほど多くはないので、満遍なく勉強し理解しておくことが重要になります。
出題範囲が狭いということもあり、過去の試験問題から少しニュアンスを変えて、また新たな問題として出てくることがほとんどです。
以下は、細かい項目に分けた過去の出題傾向と重要度を表にまとめたものです。
| 項目 | 傾向・重要度(3段階) |
| 宅建業とは | ★ |
| 宅建業の免許 | ★★★ |
| 宅建士 | ★★ |
| 営業保証金 | ★★★ |
| 保証協会制度 | ★★★ |
| 広告、契約締結時期、他 | ★★★ |
| 媒介契約の規制 | ★★★ |
| 重要事項説明 | ★★★ |
| 37条書面(契約書面) | ★★★ |
| クーリング・オフ | ★★★ |
| 手付の額の制限等 | ★★★ |
| 担保責任の制限 | ★★ |
| 手付金等の保全 | ★★★ |
| 「自ら売主規制」総合問題 | ★★★ |
| 報酬 | ★★★ |
| その他の業務上の規制 | ★★★ |
| 監督処分等 | ★★★ |
| 罰則 | ★ |
| 住宅瑕疵担保履行法 | ★★★ |
宅建業法の分野は、満点を狙って勉強しなければいけないため、捨て問題を作ってはいけません。
頻出項目
以下の10項目は、過去10年間毎年出題されている頻出項目です。
- 宅建業の免許
- 広告、契約締結時期、他
- 媒介契約の規制
- 重要事項説明
- 37条書面(契約書面)
- クーリング・オフ
- 「自ら売主規制」総合問題
- 報酬
- その他の業務上の規制
- 住宅瑕疵担保履行法
宅建業法は出題範囲が狭いため、それぞれの項目から満遍なく出題されている傾向にあります。
まずは、上記の項目を中心に学習を進め、理解できたタイミングで他の分野に着手しましょう。
宅建業法の攻略・学習法

宅建業法は、4つの分野の中で最も出題数が多いため、他の分野よりも時間を使って学習する必要があります。
この項目では、以下4つのポイントに分けて宅建業法の攻略・学習方法について解説するので、ぜひ参考にしてください。
- 他の分野よりも時間を使って学習する
- 過去問を繰り返し解く
- 弱点を克服する
- 35条書面および37条書面を完璧に覚えようとしない
それぞれ詳しく解説します。
他の分野よりも時間を使って学習する
前述した通り、宅建業法からは全体の4割が出題されます。
合格点が35~37点と仮定して、宅建業法で満点を取ることができると、残りの15~17点を他の分野すべてで補えば良いということになります。
20点満点を取りたい分野なので、ほか分野よりも時間を使って学習しなければいけません。
また、宅建業法は暗記で点数が取れる問題も多いです。
暗記で点数が取れる理由として、民法と比べて宅建業法の方が、より具体的にルールを定めた法律だからです。
他の分野よりも覚え方が簡単かつ明確なので、インプットとアウトプットをバランス良く行うと、満点を取れる可能性も高いでしょう。
過去問を繰り返し解く
宅建試験は、全体的に過去問学習が重要ですが、4つの分野の中でも宅建業法は特に必要な学習法です。
前述した通り、宅建業法は他の分野と比べて出題範囲が狭いわりに、勉強したところから満遍なく出題される傾向です。
民法は事例など数えきれないほどあるため、さまざまな出題パターンがありますが、宅建業法は問題の内容が限られてきます。
限られた問題の中で何十年も問題が作られているので、必然的に似たような言い回しのものが多くなります。
そのため、過去問を解くことは得点の近道であり、合格の鍵と言えるでしょう。
弱点をなくす
宅建業法は、本試験で満点を狙いたい分野なので、弱点は全て無くす必要があります。
得点源である宅建業法を苦手と感じてしまうと、合格は厳しくなってしまいます。
宅建業法は、勉強した箇所から満遍なく出題される分野なので、勉強した成果が目に見えてわかりやすいです。
達成感を味わいながら弱点を克服し、本試験で満点を取れるように学習を進めましょう。
35条書面および37条書面を完璧に覚えようとしない
宅建業法の攻略方法として、35条書面および37条書面を完璧に覚えようとしないことが挙げられます。
重要事項説明書の内容について例年2〜3問出題されるものの、対象となる35条および37条書面を完璧に覚えようとすると効率が悪いです。
35条書面および37条書面の学習は、アウトプット中心の過去問演習をベースに学習を進め、間違えた問題をテキストで学習する方法がおすすめです。
ただし、説明・記載が必要な事項は必ず押さえておく必要がある点は注意しましょう。
宅建業法の項目ごとの学習法

以下では、宅建業法の項目ごとの学習法について解説します。得点源となる分野なので、学習法を押さえてしっかり知識を身につけていきましょう。
宅建業法(出題数:19問)
宅建業法は、不動産業者でないお客さんに不利が生じないよう、宅建業者に対して定めたルールのことです。
業務内容と直結するため、不動産会社に勤める方にとっては当たり前のように考えることなど、仕事上の知識が勉強に活かせる項目となっています。
大きな特徴として、難問・奇問が少なく出題範囲から満遍なく出題されるため、過去問を網羅することが十分な対策となります。
満点を狙うべき分野なので、とにかく暗記と過去問学習を徹底しましょう。
スキマ時間も有効活用するために、一問一答できるアプリの利用もおすすめです。
宅建の過去問演習に役立つアプリについては「宅建アプリの特徴を徹底解説!おすすめアプリ5選も紹介」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
例題・解説①
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
② 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
③ 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
④ 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
―令和3年度【問35】
正しいのは④です。
IT重説が売買にも取り入れられたことなど、比較的新しい法改正点が問題になっているためわかりやすい問題といえます。
しばらく問題が出続ける可能性があるので、しっかり改正点を覚えておきましょう。
例題・解説②
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア:Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、当該物件の種類もしくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
イ:Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
ウ:Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
エ:Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。① 一つ
② 二つ
③ 三つ
④ 四つ―平成27年【問38】
正解は②です。
まず、イについてですが37条書面には「引渡し時期」及び「移転登記の時期」の記載は必須事項です。
また。ウは「自ら貸主」となる場合宅建業に該当しないため、37条書面への記載義務はありません。
重要事項説明書と37条書面の必要な記載事項は異なるため、それぞれしっかり覚えてひっかけなどに注意しましょう。
例題・解説③
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
① A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。
② A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。
③ Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。
④ Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、契約の解除又は損害賠償の請求は目的物の引渡しの日から1年以内にしなければならないものとする旨の特約を定めた。(改正前の問題文)
―平成30年度【問29】
この中で違反しないのは②です。
売主・買主がどちらも宅地建物取引業者であれば規定は厳しくありませんが、自らが売主で宅地建物取引業者でない買主の場合の売買契約では、買主が不利になる特約は無効となります。
仕組みを理解して問題を解いていきましょう。
住宅瑕疵担保履行法(出題数:1問)
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を販売する宅建業者等に対して、瑕疵担保責任の履行を確保するために資力確保措置を義務付けるものです。
資力確保措置とは、万が一瑕疵があった場合にきちんと賠償できるよう、宅建業者等が「保証金の供託」か「保険加入」を選択して行うことです。
毎年ほぼ同じ内容が出題されている点が特徴といえます。
特に、資力確保措置に関する知識は出題されやすいです。
資力確保措置に関する知識は、暗記と過去問学習で対策しましょう。
資力確保措置が必要な建物や対象部分、取引内容に加え、供託・保険加入時の要件がそれぞれ異なるため、数字や細かい用語に注意して覚えていってください。
例題・解説
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
① Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
② Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結する場合、当該契約は、BがAから当該新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効なものでなければならない。
③ Aが住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、A及びBは、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の瑕疵に関するAとBとの間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
④ AB間の新築住宅の売買契約において、当該新築住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はない。
―令和3年度(10月)【問45】
正しいのは③です。
売主・買主が宅建業者の場合には資力確保措置を講ずる必要はなく、買主が宅建業者でない場合は買主に不利な特約は無効となります。
過去問にも類似問題が多数あるため、忘れた場合は過去問で復習しましょう。
宅建業法が苦手な方は資格講座の受講がおすすめ

宅建業法に苦手意識が芽生えている方は、資格講座の受講をおすすめします。
前述した通り、宅建業法は本試験で50問中20問出題される分野なので、合格には学習が必須となります。
宅建業法を十分理解できていない状態で本試験に臨むと、合格できる確率が低下するため、資格講座でプロからわかりやすく教えてもらいましょう。
資格講座の中でも、通信講座を受講すると、スキマ時間で効率良く学習可能です。
社会人で学習時間が十分に確保できない方や、家事や育児で勉強に集中できない方は、自身で学習スケジュールを組みやすい通信講座を受講しましょう。
宅建業法について効率良く学びたい方は通信講座の受講がおすすめ

今回は、宅建業法の得点を上げる方法や2023年の法改正について詳しく解説しました。
宅建試験の出題範囲である4つの分野の中で、「宅建業法」は最も合格に影響を与える科目といえます。
宅建の学習を始めようと考えている方は、まずは宅建業法の出題範囲を完璧に押さえられるようにスケジュールを組みましょう。
また、宅建業法が理解できず、通信講座の受講を考えている方は「スタケン」の受講をおすすめします。
スタケンは、プロ講師が本試験攻略のポイントをわかりやすく解説しているだけでなく、受講者の方が勉強を継続しやすい環境作りにも力を入れています。
スキマ時間に効率良く学習を進めたい方や、合格を勝ち取れる宅建講座を探している方は、スタケンを受講してみてはいかがでしょうか。
なお、スタケンのサービス内容については「スタケン®のサービス内容|合格圏内を突破する勉強法も徹底解説」の記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
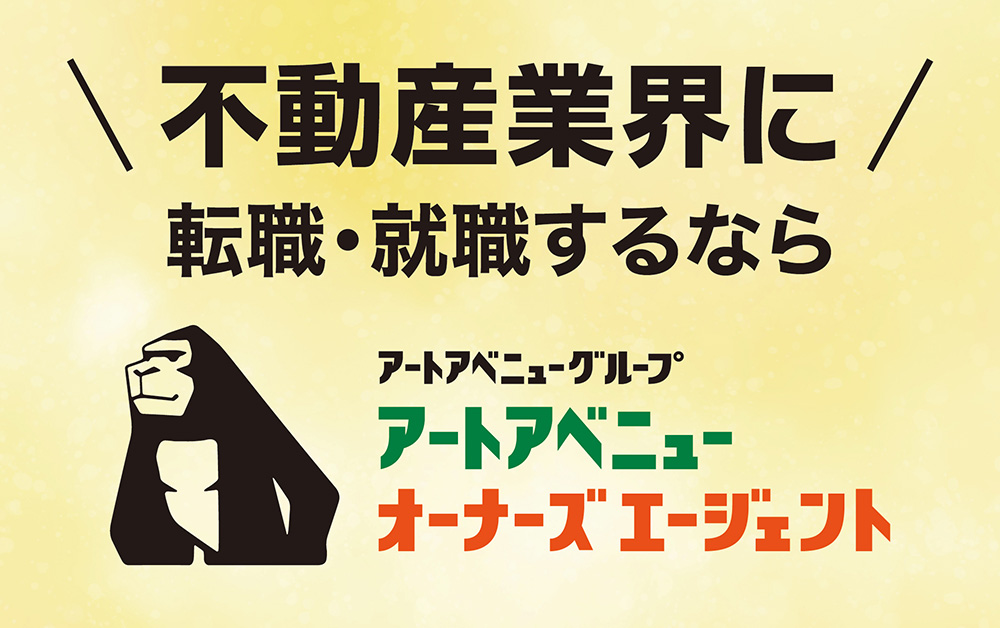
\ 積極採用中!/
最新記事 by ガースー (全て見る)
- 宅建を復習する効率的な学習テクニック - 2024年3月25日
- 宅建の難易度は?過去10年間の推移を解説 - 2024年3月25日
- 宅建合格に必要な勉強時間が200時間〜300時間って本当? - 2024年3月25日
- 2024年(令和6年度)宅建試験日&宅建申込スケジュールが決定! - 2024年3月21日